スターリングラード
 約100万人が死んだスターリングラード攻防戦をスナイパーの立場から描いた戦争映画。冒頭、主人公ヴァシリ(ジュード・ロウ)が貨物列車に乗せられてスターリングラードの河畔にたどり着く場面から「プライベート・ライアン」のような描写が炸裂する。戦闘機からの銃撃で船に乗った兵士たちはばたばたと死んでいく。逃げようとすれば、味方の治安部隊から銃殺される。さらに戦場に着いてからは銃を2人に一丁しか渡されず、無謀な突撃攻撃によって、またもばたばたと死んでいく。第2次大戦でロシアでは約2000万人が死んだといわれるが(最も犠牲者が多かった国なのである)、こういう戦い方をしていればそれも仕方ないなと思える悲惨な戦場である(愛国心だけで兵士を鼓舞し、無茶苦茶な論理で攻撃を進める在り方は戦時中の日本と同様のものに思える)。この場面が「プライベート・ライアン」よりも迫力でやや劣るのは音響効果の違いによるものだろう。加えて監督がフランス人のジャン=ジャック・アノーであることも無関係ではないような気がする。アノーにとってスターリングラードは所詮、よその国の出来事なのである。描写の重み、悲壮感、切実さが希薄だ。戦火で荒れ果てたスターリング市街のセットなどを見ると、大作のイメージがあるけれど、スナイパー同士の対決に焦点を絞ったことで映画はやや矮小さを感じさせるものになってしまった。たとえ事実であったにしても、スターリングラードの戦いというのはそういう視点で映画化するのに向いていないのだと思う。
約100万人が死んだスターリングラード攻防戦をスナイパーの立場から描いた戦争映画。冒頭、主人公ヴァシリ(ジュード・ロウ)が貨物列車に乗せられてスターリングラードの河畔にたどり着く場面から「プライベート・ライアン」のような描写が炸裂する。戦闘機からの銃撃で船に乗った兵士たちはばたばたと死んでいく。逃げようとすれば、味方の治安部隊から銃殺される。さらに戦場に着いてからは銃を2人に一丁しか渡されず、無謀な突撃攻撃によって、またもばたばたと死んでいく。第2次大戦でロシアでは約2000万人が死んだといわれるが(最も犠牲者が多かった国なのである)、こういう戦い方をしていればそれも仕方ないなと思える悲惨な戦場である(愛国心だけで兵士を鼓舞し、無茶苦茶な論理で攻撃を進める在り方は戦時中の日本と同様のものに思える)。この場面が「プライベート・ライアン」よりも迫力でやや劣るのは音響効果の違いによるものだろう。加えて監督がフランス人のジャン=ジャック・アノーであることも無関係ではないような気がする。アノーにとってスターリングラードは所詮、よその国の出来事なのである。描写の重み、悲壮感、切実さが希薄だ。戦火で荒れ果てたスターリング市街のセットなどを見ると、大作のイメージがあるけれど、スナイパー同士の対決に焦点を絞ったことで映画はやや矮小さを感じさせるものになってしまった。たとえ事実であったにしても、スターリングラードの戦いというのはそういう視点で映画化するのに向いていないのだと思う。
ウラルの山奥で育ったヴァシリは戦場で政治将校ダニロフ(ジョセフ・ファインズ)と出会い、一撃必殺の銃撃の腕を認められて、スナイパーの任務を命じられる。ドイツ軍の猛攻の前に、苦戦を強いられていたソ連軍はヴァシリの正確な射撃で息を吹き返す。その活躍はダニロフが編集する新聞で報じられ、ソ連軍の士気を高めるとともにヴァシリは英雄として知られるようになる。打撃を受けたドイツ軍は凄腕のスナイパー、ケーニッヒ(エド・ハリス)を戦場に招聘。ここから映画はヴァシリと女兵士ターニャ(レイチェル・ワイズ)の愛を絡めながら、ケーニッヒとの対決を描いていく。戦前、ドイツでケーニッヒから射撃を学んだというクリコフ(ロン・パールマン)が出てくるあたりは、こうした冒険小説的設定では常道である。ここから対決の模様を詳しく描いていけば、映画は少なくとも冒険小説ファンには支持されるものになっただろう。ところが、クリコフは大した見せ場もなくケーニッヒの銃弾に倒れてしまう。ヴァシリとケーニッヒは数度スコープを向け合うが、その描写にオリジナルなものは少ない。過去の映画で描かれたような描写が目に付くのである。
ロシア語もドイツ語もなく、登場人物がしゃべるのがすべて英語というのは興ざめではあるにしても、映画全体にしてみればささいな点。それ以前の問題として題材の取り上げ方を間違ったことに問題がある。あまりにも多くの兵士たちが亡くなったスターリングラードの戦いはスナイパー同士の対決の背景として描くには重すぎるものがあるのだ。ジャン=ジャック・アノーが本来の演出力を見せるのはターニャとヴァシリの愛の場面で、多くの兵士が眠る兵舎で秘かに愛を交わす場面には切なさがあふれている。アノーは本来、こういう描写の方が向いており、スナイパーの対決のようなアクション映画的趣向はあまり得意ではないのではないか。アノー本人が撮る題材を間違ったというべきか。力作止まりに終わったのはそんなところに原因があるようだ。
ジュード・ロウは昨年の「リプリー」に続いて、スターへの階段を順調に上っていっている感じを受ける。渋いエド・ハリスやジョセフ・ファインズ、レイチェル・ワイズも良く、出演者に関しては申し分なかった。フルシチョフ役でボブ・ホスキンスというのも意外性があっていい。
【データ】2001年 アメリカ=ドイツ=イギリス=アイルランド 2時間12分 日本ヘラルド映画配給
監督:ジャン=ジャック・アノー 製作:ジャン=ジャック・アノー ジョン・D・スコフィールド 製作総指揮:アラン・ゴダール アリサ・テイガー 脚本:ジャン=ジャック・アノー アラン・ゴダール 撮影:ロバート・フレイズ プロダクション・デザイナー:ウォルフ・クレーガー 音楽:ジェームズ・ホーナー コスチューム・デザイナー:ジャンティ・イェーツ
出演:ジュード・ロウ ジョセフ・ファインズ レイチェル・ワイズ ボブ・ホスキンス エド・ハリス ロン・パールマン ガブリエル・マーシャ=トムソン マティアス・ハービッヒ エヴァ・マッテス
ショコラ
 雪まじりの寒い北風とともに、赤いコートを羽織ったヴィアンヌ(ジュリエット・ビノシュ)とアヌーク(ヴィクトワール・テヴィソル)の親子がフランスの片田舎の村にやってくる。2人が開いたチョコレートの店は、閉鎖的で因習に凝り固まった村人の心を次第に溶かしていく。チョコレートには人の心を解放する南米の秘薬が含まれており、ヴィアンヌは明確に因習の打破を意図して旅から旅の生活を続けているのである。しかし、ラスト近く、ヴィアンヌ自身も因習(あるいは自分はこうあらねばならない、という固定観念)に捕らわれていたことが分かる。この展開を見て、これがオリジナル脚本だったら、すごいなと思ったが、ちゃんと原作があるそうだ。それほどさまざまな寓意を持たせた物語なのである。ラッセ・ハルストレムはこの含蓄のある話をチョコレートのように甘く心地よく映画化している。改めてハルストレムのうまさを認識させられる出来である。
雪まじりの寒い北風とともに、赤いコートを羽織ったヴィアンヌ(ジュリエット・ビノシュ)とアヌーク(ヴィクトワール・テヴィソル)の親子がフランスの片田舎の村にやってくる。2人が開いたチョコレートの店は、閉鎖的で因習に凝り固まった村人の心を次第に溶かしていく。チョコレートには人の心を解放する南米の秘薬が含まれており、ヴィアンヌは明確に因習の打破を意図して旅から旅の生活を続けているのである。しかし、ラスト近く、ヴィアンヌ自身も因習(あるいは自分はこうあらねばならない、という固定観念)に捕らわれていたことが分かる。この展開を見て、これがオリジナル脚本だったら、すごいなと思ったが、ちゃんと原作があるそうだ。それほどさまざまな寓意を持たせた物語なのである。ラッセ・ハルストレムはこの含蓄のある話をチョコレートのように甘く心地よく映画化している。改めてハルストレムのうまさを認識させられる出来である。
人はさまざまな固定観念に縛られているのだと思う。岸田秀「ものぐさ精神分析」によれば、その最たるものは親の影響なのだが、社会の規範であったり、宗教であったり、会社の規則であったりするだろう。そうした規則や規範に人は知らず知らずのうちに、ねじを巻かれて生きている。それに従っている限りは心配がないからである。映画の中で固定観念の権化となっているのが村長で伯爵のレノ(アルフレッド・モリーナ)。断食の時期にチョコレートの店を開き、教会にも行かないヴィアンヌをレノは悪魔のように非難する。実際、赤いコートを着て現れ、不思議なチョコレートを売る親子は魔法使いのようだ。この設定、スティーブン・キング「ニードフル・シングス」に似ている(あちらは本当の悪魔だったが)。チョコレートの効果で倦怠期の夫婦は情熱を取り戻し、ある老人は長年の秘めた思いを打ち明ける。暴力を振るう夫からジョゼフィーヌ(レナ・オリン)は独立する。そうした効果を見てもレノは規範を守ることを最優先に考えてしまう。これと対照的なのがヴィアンヌの生き方であり、後半に登場するジプシーのルー(ジョニー・デップ)なのである。不自由な体にもかかわらず自分の思う通りに生きているアルマンド(ジュディ・デンチ)と娘カロリーヌ(キャリー=アン・モス)の関係も自由と規則の対立を端的に表している。
原作ではレノは神父だそうだ。ハルストレムは人の心を抑えつけるのが宗教であるとの図式を嫌って役を変えたそうだが、それは正しい判断と思う。これによってさまざまな場合に当てはめて考えることができるようになっている。そして因習に縛られずに生きてきたはずのヴィアンヌが実は母親の教えに縛られていたことが鮮明になるショットが挿入される。母親の灰の入った壺を誤って娘が割ってしまうことによって、ヴィアンヌは初めて我に返る。旅から旅への自由な生活と思われていたことが実は母親の教えに従っていただけだったことを理解するのである。
空撮で、おとぎ話に出てくるような村の全景を見せたショットから映画は緩やかにこうした人間関係を描き出していく。原作のポイントを逃さなかったと思われるロバート・ネイスン・ジェイコブスの脚本もいい。ジュリエット・ビノシュ、レナ・オリン、キャリー=アン・モス、ジュディ・デンチらの女優陣がとにかくうまいし、娘役のヴィクトワール・テヴィソルも美少女の輝きを見せ、将来のスターになりそうな予感。男優陣も凝ったメイクのアルフレッド・モリーナ、ジョニー・デップが良く、小さい作品ではあるけれど、好感の持てる映画である。
【データ】2000年 アメリカ 2時間1分 アスミック・エース、松竹配給
監督:ラッセ・ハルストレム 製作:デヴィッド・ブラウン レスリー・ホールラン キット・ゴールデン 原作:ジョアン・ハリス 脚本:ロバート・ネイスン・ジェイコブス 撮影:ロジャー・ブラット プロダクション・デザイナー:デヴィッド・グロップマン 衣装:レネー・エールリッヒ 音楽:レイチェル・ポートマン
出演:ジュリエット・ビノシュ ジョニー・デップ ジュディ・デンチ レナ・オリン アルフレッド・モリーナ ピーター・ストーメア キャリー=アン・モス レスリー・キャロン ジョン・ウッド ヒュー・オコナー ヴィクトワール・テヴィソル
タイタンズを忘れない
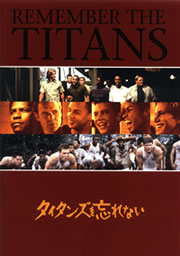 肩肘張った社会派の大作ではなく、エンタテインメントとしてさわやかに感動的に描かれた人種差別撤廃映画とでもいうべき作品。1971年、ヴァージニア州アレキサンドリアにある高校のフットボールチーム「タイタンズ」を描いた実話で、人種の壁を超えて一つになったチームが連戦連勝し、町の人々も巻き込んでいく過程が綴られる。ヘッド・コーチ役で主演のデンゼル・ワシントンはこうした映画には欠かせない存在だが、共演のアシスタント・コーチ役ウィル・パットンの渋い抑えた演技が光り、何よりも個性あふれる高校生たちの群像劇が実にいい。この映画まず、スポーツを通じた青春学園ドラマの側面がよくできているのが幸いした。硬さとエンタテインメントがほどよいさじ加減で、うまくまとまっている。監督のボアズ・イエーキンはこれがメジャーデビュー。製作のジェリー・ブラッカイマーとよくコンビを組むマイケル・ベイなどより演出的にずっとまともである。人種差別を描いた映画としてはスパイク・リー作品のような鋭さには欠けるし、甘い部分も散見されるが、こういうバランスの取れた大衆的な映画の方がテーマを伝えるためには効果的な場合がある。
肩肘張った社会派の大作ではなく、エンタテインメントとしてさわやかに感動的に描かれた人種差別撤廃映画とでもいうべき作品。1971年、ヴァージニア州アレキサンドリアにある高校のフットボールチーム「タイタンズ」を描いた実話で、人種の壁を超えて一つになったチームが連戦連勝し、町の人々も巻き込んでいく過程が綴られる。ヘッド・コーチ役で主演のデンゼル・ワシントンはこうした映画には欠かせない存在だが、共演のアシスタント・コーチ役ウィル・パットンの渋い抑えた演技が光り、何よりも個性あふれる高校生たちの群像劇が実にいい。この映画まず、スポーツを通じた青春学園ドラマの側面がよくできているのが幸いした。硬さとエンタテインメントがほどよいさじ加減で、うまくまとまっている。監督のボアズ・イエーキンはこれがメジャーデビュー。製作のジェリー・ブラッカイマーとよくコンビを組むマイケル・ベイなどより演出的にずっとまともである。人種差別を描いた映画としてはスパイク・リー作品のような鋭さには欠けるし、甘い部分も散見されるが、こういうバランスの取れた大衆的な映画の方がテーマを伝えるためには効果的な場合がある。
アレキサンドリアは保守的な田舎町。根強い黒人差別が残り、「この町の黒人には屈辱と絶望しかない」という状況である。しかし公民権運動の流れで黒人と白人の高校が統合され、フットボール部のコーチに黒人のハーマン・ブーン(デンゼル・ワシントン)が赴任してくる。それまでヘッド・コーチだったビル・ヨースト(ウィル・パットン)はアシスタントに降格。ハーマンの着任には人種差別撤廃の象徴的意味があったらしいが、町の有力者たちは失敗すれば、すぐにハーマンを辞めさせようとしていた。生徒たちも大人に負けず、敵対心を燃やしている。ハーマンは2週間の合宿でハードな練習を重ねるとともに、生徒たちにお互いを理解させることに成功する。ハーマンとビルも最初は敵対するが、チームの勝利に関して目的は同じ。次第に心を通わせていく。最初の試合では全員が白人のチームと対戦。ビルの的確なアドバイスでタイタンズは勝利する。その後も順調に勝ち進み、州大会でも躍進を続ける。その活躍を見て町の人たちはタイタンズの姿勢に拍手を送るようになる。
生徒の中で白人グループのリーダーであるゲリー(ライアン・ハースト)と黒人グループのリーダー、ジュリアス(ウッド・ハリス)との交流がいい。黒人と仲良くし始めたことで、ゲリーはガールフレンドと親友を失うことになるが、それでもひたむきさを忘れない。終盤、ゲリーは不幸な事故に遭うが、その後の力強い生き方には共感を覚える。転校生を演じたロニー(キップ・パルデュー)や黒人のクォーターバック役ピーティ(ドナルド・フェゾン)、名前が分からないが、人の良い太っちょの白人選手ら生徒たちのそれぞれの描写がさわやかだ。黒人の高校生が白人専用のパブに入るのを断られたり、親たちの対立など多くの人種差別の例も点景として描かれ、物語に厚みを与えている。さまざまな場面での人種間の対立と和解が描かれており、脚本のグレゴリー・アレン・ハワードは良い仕事をしたと思う。デンゼル・ワシントンは過去の映画では熱演が空回りした場合もあったが、ボアズ・イエーキンの演出はワシントンだけに重きを置かず、ウィル・パットンや生徒たちをバランスよく描き、これを回避するのに成功している。
【データ】2000年 アメリカ 1時間45分 ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ提供 配給:ブエナ・ビスタ・インターナショナル
監督:ボアズ・イエーキン 脚本:グレゴリー・アレン・ハワード 製作:ジェリー・ブラッカイマー チャド・オーメン 製作総指揮:マイク・ステンソン マイケル・フリン 撮影:フィリップ・ルースロ 美術:デボラ・エヴァンス 衣装デザイン:ジュディ・ラスキン・ハウエル 音楽:トレバー・ラビン
出演:デンゼル・ワシントン ウィル・パットン ウッド・ハリス ライアン・ハースト キップ・パルデュー ドナルド・フェゾン ハイデン・パネティエーリ
15ミニッツ
 「インサイダー」でアル・パチーノが製作する番組は「60ミニッツ」といったが、この映画のタイトルはそれとは関係なく、アンディー・ウォーホールの「だれでも15分間は有名人でいられる時代が来る」との言葉から取っている。当然のことながら、メディア批判を意図したわけだ。しかし、批判の矛先は鈍い上に、ドラマの構成にも破綻が目立つ。メディア批判なのか、刑事アクションなのか、描写がどちらも中途半端である。この程度で社会派云々といわれると、苦笑せざるを得ない。テレビ局の描写はカリカチュアに近いし、犯人像もリアリティーに欠ける。監督・脚本のジョン・ハーツフェルド、映画製作に対する姿勢が安易なのではないか。25年前の「ネットワーク」(シドニー・ルメット監督)に負けるようでは、こういう題材を撮る意味はない。
「インサイダー」でアル・パチーノが製作する番組は「60ミニッツ」といったが、この映画のタイトルはそれとは関係なく、アンディー・ウォーホールの「だれでも15分間は有名人でいられる時代が来る」との言葉から取っている。当然のことながら、メディア批判を意図したわけだ。しかし、批判の矛先は鈍い上に、ドラマの構成にも破綻が目立つ。メディア批判なのか、刑事アクションなのか、描写がどちらも中途半端である。この程度で社会派云々といわれると、苦笑せざるを得ない。テレビ局の描写はカリカチュアに近いし、犯人像もリアリティーに欠ける。監督・脚本のジョン・ハーツフェルド、映画製作に対する姿勢が安易なのではないか。25年前の「ネットワーク」(シドニー・ルメット監督)に負けるようでは、こういう題材を撮る意味はない。
暴力報道を志向するニュース番組「トップ・ストーリー」のスタッフをスケッチした後、映画は東欧からニューヨークに来た2人の男エミル(カレル・ローデン)とウルグ(オレッグ・タクタロフ)が、アパートでかつての仲間とその妻を衝動的に殺す場面を描く。ウルグはビデオマニアでその殺人現場をビデオ撮影。2人は事故死に見せかけ、アパートに放火する。殺害の様子は殺された妻の友人ダフネ(ヴェラ・ファミーガ)が目撃していた。ニューヨーク市警の刑事エディ・フレミング(ロバート・デ・ニーロ)はその現場で消防局の放火捜査班員ジョーディ・ワーソー(エドワード・バーンズ)と出会う。ジョーディは死体の状況から事故死ではなく、殺人であると指摘。2人は行動を共にし、殺人を続けるウルグとエミルを追いつめていく。
このまま進めば、普通の刑事アクションになるはずだが、映画はここで無理矢理メディア批判に方向転換する。ウルグとエミルはアメリカのテレビがセンセーショナルな映像を高く買い上げることを知り、有名人を殺す現場を「トップ・ニュース」に高く売りつけようとする。その標的に選んだのが、ニューヨークで最も有名な刑事エディだった。逮捕されても精神異常を装い、精神病院に収容された後に正常を訴えて退院するという計画。正常であることが分かってもダブル・ジョパディー(一事不再理=二重処罰の禁止)の原則で再び罪には問われないという計算である。これが著しくリアリティーを欠くのだが、さらにメディア批判的展開でありながら、結局、ラストを刑事アクション的場面で終わらせてしまうのではどうしようもない。
ニューヨークが舞台なので、タイムズ・スクウェアやセントラル・パークなどニューヨークの風景がふんだんに出てくるのは良く、目抜き通りで繰り広げられるアクションはまずまず。ロバート・デ・ニーロはこういう映画でもちゃんと演技に手を抜かず、軽妙と重厚さを併せ持った演技を見せる。相手役のエドワード・バーンズもなかなか良く、この2人を中心にした純粋な刑事アクションを見たかった思いがする。「ダーティ・ハリー」に象徴されるように、こういう刑事コンビで、どちらかが危機に陥るのは定石的な展開だが、そこを少しひねり、意外性を持たせた点は評価できる。ただし、デ・ニーロが消えた後はノー・スターの映画になってしまい、画面から重みがなくなっている。本筋に絡まない無駄な描写も多く、ジョン・ハーツフェルドの演出にはどうも締まりがない。
【データ】2001年 アメリカ 2時間1分 配給:日本ヘラルド映画
監督:ジョン・ハーツフェルド 製作:ニック・ウェクスラー キース・アディス デヴィッド・ブロッカー ジョン・ハーツフェルド 製作総指揮:クレアー・ラドニク・ポルスティン 脚本:ジョン・ハーツフェルド 撮影:ジャン・イヴ・エスコフィエ プロダクション・デザイン:メイン・バーク 音楽:J・ピーター・ロビンソン 衣装デザイン:エイプリル・フェリー
出演:ロバート・デ・ニーロ エドワード・バーンズ ケルシー・グラマー エイヴリー・ブルックス メリーナ・カナカレデス カレル・ローデン オレッグ・タクタロフ ヴェラ・ファミーガ ジョン・ディレスタ シャーリーズ・セロン