イースタン・プロミス
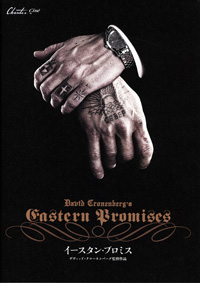
パンフレットによれば、「イースタン・プロミス」とは東欧組織による人身売買契約の意味とのこと。キリスト教絡みの意味があるのかと思ったら、内容をそのまま表したものだった。イギリスのロシアン・マフィアを描くこの作品、最初からバイオレンスに彩られている(暴力描写でR-18というのも暴力に甘い日本では珍しい)。デヴィッド・クローネンバーグの前作「ヒストリー・オブ・バイオレンス」は我慢に我慢を重ねた男が最後に爆発するという、まるで高倉健や鶴田浩二が出て来る任侠映画のような筋立てだったが、今回は菅原文太が出てくる実録路線のヤクザ映画を彷彿させる。
冒頭、理髪店の椅子に座った男が首を切られるシーンから凄絶な描写。従来のマフィア映画であれば、剃刀をスーッと横に滑らせるだけだが、この映画ではのこぎりの歯を引くように左右にグビグビと動かして喉笛を切る。マフィアを描いたといっても社会派の映画ではさらさらなく、リアルなバイオレンス描写が前作から続いてのクローネンバーグの関心なのではないかと思えてくる。バイオレンスと緊張感に満ちた作品だ。
内容はタイトル同様に明快である。助産師のアンナ(ナオミ・ワッツ)が働く病院に妊娠中のロシア人少女が胎盤剥離で搬送される。少女は死ぬが、子供は生まれる。少女の身元を探すためアンナは少女が持っていたカードからロシアン・レストランを訪ね、店の前でニコライと名乗る男(ヴィゴ・モーテンセン)に出会う。レストランの主人セミオン(アーミン・ミューラー=スタール)は温厚そうな人柄だったが、少女が残した日記に強い興味を示す。日記はロシア語で書かれており、アンナには読めない。ロシア人の叔父に訳してもらうと、そこにはロシアン・マフィアの恐ろしさが綴られていた。セミオンはマフィアのボスで、ニコライはその息子キリル(ヴァンサン・カッセル)の運転手だった。
スティーブ・ナイトの脚本は過去によくあるマフィア映画の設定をロシアン・マフィアに移し替えたもので、取り立ててよく出来ているわけではない。ボスの息子が酒浸りでダメな男だったり、そのそばに優秀なニコライがいる設定など何度も見た覚えがある(ちなみに、スティーブ・ナイトは別名で本当はスティーブン・ナイト。作品によって最後のnを取ったり取らなかったりしているのは何か理由があるのだろうか)。それなのにこんなに緊張感のある映画に仕上がるのはやっぱり映画は監督に左右されるからだろう。クローネンバーグのギャング映画はマーティン・スコセッシともコーエン兄弟とも異なる独自のものだ。サウナで全裸のモーテンセンがチェチェンマフィアの男2人と繰り広げるアクションは凄絶で極めてリアル。
ヴィゴ・モーテンセンは冷徹な男をクールに演じて隙がない。ヴァンサン・カッセルのダメ男ぶりもうまいと思う。どちらも演技に奥行きがあった。
