映画とネットのDIARY(tDiary版)
検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。
【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2004年10月09日 [Sat]
■ MLの記事HTML化
さくらインターネットでMLの設定がGUIでできるようになった。投稿記事のHTML化もできる。さっそく作ってみると、メール一覧の日付がすべてat 70/01/01 09:00:00となる。これはバグでしょう。あくまで試用、本サービスではないから仕方がないか。HTMLの自動生成をチェックしておくと、その後は投稿があるたびにHTML化される。こちらの方は日付も正常。
デザインはいろいろカスタマイズしたいところ。Namazuで検索できるようにすると、さらに便利ですね。
■ [MOVIE]「デビルマン」
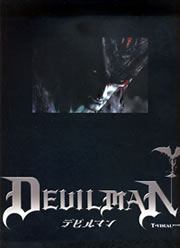 ブライアン・デ・パルマ「ミッドナイトクロス」の冒頭で、シャワー室で襲われる女の叫び声を録音していた録音技師のジョン・トラボルタが、女優のあまりの下手さ加減に匙を投げるシーンがある。「デビルマン」を見ていてそれを思い出した。中盤、主人公の不動明(伊崎央登)がデーモンであることを養父の牧村(宇崎竜童)に知られて上げる叫び声がなんとも迫力のないものなのである。終盤にもう一度、叫び声を上げるシーンがあるが、そこも同じ。これほど真に迫らない叫び声は初めて聞いた。この程度の叫び声でなぜ那須博之監督がOKを出したのか理解に苦しむ。感覚が狂っているのか、現場をコントロールできなかったのか、時間が足りなかったのか。いろいろあるだろうが、こういうところでOKする姿勢が映画全体に波及してしまっている。主人公だけでなく、他の出演者の演技にもまるでリアリティがない。6月公開予定を延期してCGをやり直したそうだが、出演者の演技も最初からやり直した方が良かった。いや、その前に脚本を作る段階からやり直した方が良かっただろう。永井豪の最高傑作とも言えるあの原作がなぜ、こんなレベルの映画になってしまうのか。「スクール・ウォーズ HERO」とは違って、「デビルマン」の物語を本当に理解しているスタッフはいなかったのではないか。
ブライアン・デ・パルマ「ミッドナイトクロス」の冒頭で、シャワー室で襲われる女の叫び声を録音していた録音技師のジョン・トラボルタが、女優のあまりの下手さ加減に匙を投げるシーンがある。「デビルマン」を見ていてそれを思い出した。中盤、主人公の不動明(伊崎央登)がデーモンであることを養父の牧村(宇崎竜童)に知られて上げる叫び声がなんとも迫力のないものなのである。終盤にもう一度、叫び声を上げるシーンがあるが、そこも同じ。これほど真に迫らない叫び声は初めて聞いた。この程度の叫び声でなぜ那須博之監督がOKを出したのか理解に苦しむ。感覚が狂っているのか、現場をコントロールできなかったのか、時間が足りなかったのか。いろいろあるだろうが、こういうところでOKする姿勢が映画全体に波及してしまっている。主人公だけでなく、他の出演者の演技にもまるでリアリティがない。6月公開予定を延期してCGをやり直したそうだが、出演者の演技も最初からやり直した方が良かった。いや、その前に脚本を作る段階からやり直した方が良かっただろう。永井豪の最高傑作とも言えるあの原作がなぜ、こんなレベルの映画になってしまうのか。「スクール・ウォーズ HERO」とは違って、「デビルマン」の物語を本当に理解しているスタッフはいなかったのではないか。
「外道! きさまらこそ悪魔だ」と、原作の不動明は叫ぶ。悪魔特捜隊本部で悪魔に仕立てられて惨殺された牧村夫妻を発見し、そばにいた人間たちに怒りの声を上げるのだ。「おれのからだは悪魔になった…。だが、人間の心は失わなかった! きさまらは人間のからだを持ちながら悪魔に! 悪魔になったんだぞ。これが! これが! おれが身をすててまもろうとした人間の正体か!」。
映画にも「悪魔はお前ら人間だ!」というセリフはあるが、それを叫ぶのは不動明ではない。デーモンに合体された少女ミーコ(渋谷飛鳥)である。なぜ、こういう改変を行うのか。主人公にこのセリフを叫ばせなければ、その後の展開がおかしくなってしまう。原作の不動明は愛する美樹を殺した人間たちを一掃し、同時に怒りの矛先を人間たちの心理を利用して自滅させようとした飛鳥了に向ける。映画の明は人間は殺さず、了との対決に臨む。これでは愛する者たちを殺された主人公の怒りが伝わってこない。だからドラマとして貧弱になってしまうのだ。
脚本は那須真知子。2時間足らずの上映時間に全5巻の原作を詰め込むのは所詮無理な話ではある。しかし、無理は無理なりに何らかの工夫が必要だろう。単に原作をダイジェストにしただけで脚本家が務まるのなら、脚本家はなんと気楽な商売かと思う。那須真知子、監督と同じくSFに理解があるとは思えない。ならば、そういう仕事は引き受けるべきではなかっただろう。原作の飛鳥了は終盤まで自分の正体を知らない。映画では早々に正体をばらしてしまう。原作を思い切り簡略化した話で、それを見るに堪えない演出で語ろうというのだから、つまらなくなるのは目に見えている。
このほか、不動明とデビルマンの中間みたいなメイクアップがまるで意味をなさないとか、妖鳥シレーヌ(富永愛)の扱いが彩り程度のものであるとか、原作のラストの後に余計なメッセージを付け加えているとか、やり直したCGの場面が少ないとか、ボブ・サップやKONISIKIを使う意味が分からないとか、冒頭にある少年2人のシーンがお粗末すぎるとか、さまざまな不満な点がある。ついでに言うと、こんな雑な映画を作って公開する意味も分からない。こんなことなら、アニメでリメイクした方が良かったのではないか。
2005年10月09日 [Sun]
■ 「蝉しぐれ」(NHKドラマ)
気になったのでDVDをamazonで買って見た。全7話、315分。いきなり中年の文四郎とおふくが再会するシーン(原作のエピローグに当たる部分)で始まり、25年前を回想し始める構成に驚く。僕が3日の日記に書いたようなことは黒土三男、ちゃんと考えていたのだ。ただ、毎回、回想の形で話が進むと、何だか鼻についてくる。はっきり言って4話目まで(「嵐」「蟻のごとく」「ふくと文四郎」「秘剣村雨」)は極めて平凡な出来で、「やっぱりテレビドラマはダメだよなあ」と悪口を山のように考えながら見ていた。父親の切腹前から大八車で遺体を運ぶシーンまでが描かれる第2話などは映画の方がよほどうまい描写をしている。というか、映画で良かったのはここだけだったので、監督にはテレビの不備を補いたい気持ちがあったのかもしれない。
里村家老の陰謀に絡む5話「罠」と6話「逆転」がいい出来。ここの面白さは主にチャンバラの面白さだ。ちゃんと秘剣村雨も登場する。ここがあまりにいいので、7話「歳月」は付け足しみたいに感じるが、原作には忠実である。おふくが「あの日も今日のように暑い日でした」と語りかけるのは大八車を一緒に引いた日のことであり、この方が蛇に指を噛まれた思い出よりはよほど説得力がある。映画ではなぜ、こういう形にしなかったのか、理解に苦しむ。
全体的な脚本の作りは映画とよく似ている。映画の脚本はここから登場人物やエピソードを削り、時間の制約で語れなかった部分のエピソードを変えただけのように思う。NHKの〜金曜時代劇・ご感想掲示板〜には映画よりテレビの方が良かったという声ばかりが並んでいる。確かにまとまりでは十分な時間のあるテレビの方が上なのだが、特に前半の描写の深みは映画の方が勝っている。
テレビドラマは基本的に筋しか語れない。見ていて面白い映像というのはあまりなく、映像で語るという方法もこのドラマに限って言えば、希薄だった。そう感じるのはナレーションが多いからかもしれない。もっとも、映画に比べると驚くほど描写がない、というのはどのテレビドラマを見ても感じることではある。
■ ハリガネムシ
家族が外でワイワイ騒いでいるので何かと思ったら、ハリガネムシだった。犬がカマキリを食べたら、カマキリの体内からこの虫が出てきたのだという。当たり前だ。僕らは小さいころ、これをカマキリの本体と呼んでいた。カマキリが死ぬと必ずお尻の方から出てくるのだ。
ハリガネムシは水の中で生まれ、それを食べた水生昆虫をカマキリが食べることでカマキリに寄生する。体長は15センチほど。出てくるのはカマキリが死んだときだけでなく、水に近づくと、カマキリの腹を突き破って出てくるのだそうだ。カマキリから脱出するハリガネムシにはその様子を撮影した動画がある。腹を突き破って出てくるとはまるでエイリアンみたいなやつだな。
■ シグマ11.1倍高倍率ズームレンズ 18-200mm F3.5-6.3 DC
シグマのデジタルカメラ専用ズームレンズ。楽天(カメラのミツバ)に注文したのが届いた。昨日の午前10時過ぎに注文して午後7時過ぎに注文確認書がメールで届き、きょうの午後1時過ぎには現物が届いてしまった。届くのは来週後半かと思っていたのに、メチャクチャ速い。在庫があったにしても速い処理だと思う。こんなに速いと、逆に注文があまりない店なのではないかと思ってしまいますね。それでも楽天のショップでは価格が一番安かったのでいいのですがね。
普段はNikon D70レンズキットに付いてきた18−70ミリを使っている。ちょっと遠くのものを撮影する時にはこれだと不便。70−300ミリも持っているのだが、大きいので望遠専用の用途に使う時以外は持って行くのが面倒だ。18−200ミリなら、たいていの用途はこれ1本でまかなえる。
シグマのズームのリングは回転方向がNikonと逆。ま、慣れれば、これでも問題ない。AFの反応はスムーズ。テレ端の撮影倍率がタムロンより小さいとかの弱点はあるそうだ(【伊達淳一のレンズが欲しいッ!】タムロンvsシグマ 高倍率ズーム対決【続報】)が、細かな部分にこだわる方ではないので、値段相応のこれで十分な感じ。
■ 「セルラー」(DVD)
携帯電話を軸にしたサスペンス・アクション。わけの分からないまま5人の男たちに自宅から誘拐された女(キム・ベイシンガー)が壊れた電話の線を必死につないで、かけた電話がある男(クリス・エバンス)の携帯にかかる。監禁されている場所も分からないので電話が切れたら命がないというシチュエーションの中、アイデアを詰め込んだ脚本がよい出来だ。B級だが、予想より面白かった。なぜ警察に事件を届けられないのかという部分をちゃんと押さえており、あとはジェットコースター的展開で見せる。悪役側にジェイソン・ステイサム、定年を迎えた刑事にウィリアム・H・メイシー。ベイシンガーが老けたのには少しがっかり。
監督は「デッド・コースター ファイナル・デスティネーション2」のデヴィッド・R・エリス。原案は「フォーン・ブース」のラリー・コーエン。脚本はクリス・モーガンだが、製作初期に「バタフライ・エフェクト」のJ・マッキー・グラバーが関わっていたとのこと。クレジットはされていない。
2011年10月09日 [Sun]
■ 「猿の惑星:創世記(ジェネシス)」
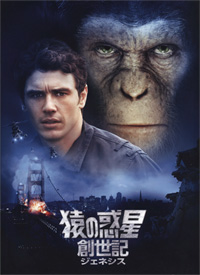
クライマックス、騎馬警官隊がゴールデンゲート・ブリッジの猿の群れを襲うシーンは「猿の惑星」第1作の序盤、馬に乗った猿による人間狩りのシーンの恐怖を容易に思い起こさせる。これ以外にも行方不明になった宇宙船を報じる新聞が出てきたり、最初に猿がしゃべる言葉が「No!(いやだ!)」であったり、コーネリアという名前の猿が出てきたり等々、旧作につながるシーンが至るところにあり、旧作を見てきた映画ファンはニヤリとするだろう。しかし、まったく見ていなくても問題はない。監督のルパート・ワイアットは一部のファンに対して映画を作るような狭い了見で映画を作ってはいない。というよりも、映画興行的にもこれは当然だろう。ワイアットはアルツハイマー治療薬を投与されたメス猿がジェネシス社で暴れる序盤を迫力たっぷりに描き、観客の度肝を抜く。そこから一気呵成にラストまで突っ走る。映像に力があふれており、これはシリーズ第1作に匹敵する出来栄えと言って良い。
旧シリーズは第5作まで作られた。第2作「続・猿の惑星」のラストで地球は核兵器によって壊滅し、シリーズも終わりかと思われたが、ここから旧シリーズのスタッフは驚天動地の続きを考える。ドル箱シリーズを続けるためには不可能を可能にするアイデアだって思いつくのだ。すなわち3作目の「新・猿の惑星」は第2作のラスト、宇宙船で逃げたコーネリアスとジーラが地球の大爆発の影響で過去にタイムスリップするという設定。未来が猿によって支配されることを知った人間たちによってコーネリアスとジーラは殺されてしまうが、その子供マイロ(後のシーザー)は生き残る。ラスト、サーカスの檻の中で「ママ…」とつぶやく幼いマイロは第4作「猿の惑星 征服」で反乱を起こす猿たちのリーダー、シーザーとなるわけだ。ついでに書いておけば、第5作「最後の猿の惑星」(併映は配給会社が意図したのかどうか知らないが、チャールトン・ヘストン主演のSF「ソイレント・グリーン」だったと思う)とティム・バートンによる2001年のリメイク(本人はリ・イマジネーション=再創造と言っていた)「Planet of The Apes 猿の惑星」はなくても全然かまわない出来だった。
というわけで今回の新作は第3作と第4作をなかったことにした語り直しという位置づけとなる。旧作では猿の進化の理由が説明されなかったが、今回はウィルス進化論を適用している。主人公のウィル(ジェームズ・フランコ)が開発したアルツハイマー治療薬は遺伝子操作を行うウィルスなのである。このあたりはキネ旬10月下旬号の「『ウィルス進化論』を裏付ける映画のリアリティ」が詳しく、これを書いた医学博士の中原英臣は「この40年間の科学の進歩が、SF映画でしかなかった『猿の惑星』の起源という大きな謎を解明しつつある」とまで書いている。
そういうSF的設定に隙がないところも良いのだけれど、ここはやはり1時間46分という賢明な上映時間に猿たちの蜂起に至る過程を圧倒的な迫力で、しかも情感をこめてまとめ上げたルパート・ワイアットの手腕を評価すべきだろう。加えてWETAデジタルが担当した猿のCG(パフォーマンス・キャプチャー)は本物の猿と見分けがつかない見事な出来だ。シーザーを演じたアンディ・サーキスは「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのゴラムとピーター・ジャクソン版「キング・コング」を演じた俳優なのだそうだ。
作品への評価が高い上に、ヒットもしているので間違いなく続編が作られるだろう。尻すぼみになった旧シリーズの轍を踏まず、充実したシリーズになることを祈りたい。
