映画とネットのDIARY(tDiary版)
検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。
【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2005年03月18日 [Fri]
■ 月額2,900円でしゃべり放題、5月1日から音声定額プラン導入 - ウィルコム
ついでに7月1日からはPCと接続したパケットも定額(2,100円)となり、月額5,000円で完全定額が実現するという。僕は携帯をあまり使わない方だが、ウィルコムの携帯(というかPHSだが)がいいのは、京セラのAH-K3001Vの場合、Operaを搭載して、普通のWebサイトが見られることと、PC用のメールアドレスが使えること(POP、SMTP対応メーラー搭載)。しかも全角2万文字まで使えるのでPCと同じ感覚でメールのやりとりができる。定額料金での通信速度はx1(32kbps)と遅いので、自宅での常時接続には適さないが、外出先では十分使えるだろう。
カメラは11万画素だし、音楽も聞けないのは今の流行からは外れているけれど、個人的にはかなり魅力的。携帯のパソコン化推進としてウィルコムの方針は興味深い。
■ [MOVIE] 「ロング・エンゲージメント」
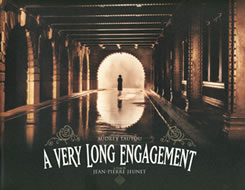 セバスチャン・ジャプリゾと言えば、「さらば友よ」でも「雨の訪問者」でもなく、個人的には「殺意の夏」の作家。あの映画の終盤、止められない不幸な殺人計画の描写はとても皮肉で面白かった。イザベル・アジャーニもこれが一番きれいだったと思う。そのジャプリゾ原作「長い日曜日」に惚れ込んだジャン=ピエール・ジュネが「アメリ」に続いてオドレイ・トトゥを主演に迎えたのがこの映画。戦死したと思われた恋人を探す女の話である。基本的な構造はミステリだが、ジュネの演出はラブストーリーへの比重が大きく、それに第一次大戦の戦場の悲惨な描写が加わっている。この3つの要素のうち、ミステリの部分の手際があまりうまくない。映画を見て、ああ、ああ、なるほどねとは思うのだけれど、驚くような描写はない。そういう風に演出していないのである。ジュネ、ミステリ的な部分にはあまり興味がないらしい。ラブストーリーの部分を強調したいなら、ミステリの部分をもっとすっきりさせた方が良かっただろう。登場人物を絞り込み、真相の描き方にアクセントを付ける必要があったと思う。
セバスチャン・ジャプリゾと言えば、「さらば友よ」でも「雨の訪問者」でもなく、個人的には「殺意の夏」の作家。あの映画の終盤、止められない不幸な殺人計画の描写はとても皮肉で面白かった。イザベル・アジャーニもこれが一番きれいだったと思う。そのジャプリゾ原作「長い日曜日」に惚れ込んだジャン=ピエール・ジュネが「アメリ」に続いてオドレイ・トトゥを主演に迎えたのがこの映画。戦死したと思われた恋人を探す女の話である。基本的な構造はミステリだが、ジュネの演出はラブストーリーへの比重が大きく、それに第一次大戦の戦場の悲惨な描写が加わっている。この3つの要素のうち、ミステリの部分の手際があまりうまくない。映画を見て、ああ、ああ、なるほどねとは思うのだけれど、驚くような描写はない。そういう風に演出していないのである。ジュネ、ミステリ的な部分にはあまり興味がないらしい。ラブストーリーの部分を強調したいなら、ミステリの部分をもっとすっきりさせた方が良かっただろう。登場人物を絞り込み、真相の描き方にアクセントを付ける必要があったと思う。
1917年の西部戦線(もちろん、ドイツ側から見た場合の西部戦線であり、フランスではこうは呼ばない)、ビンゴ・クレピュスキュル。フランス軍の5人の兵士が処刑に引き立てられる。5人とも軍を抜けようとして自傷したことで軍法会議にかけられ、処刑命令が下った。5人は武器も持たずに中立地帯に追放される。そこはフランス軍とドイツ軍が対峙する中間地点にあり、双方からの激しい攻撃によって5人とも死亡したと思われた。その中にはブルターニュ地方に住むマチルド(オドレイ・トトゥ)の恋人マネク(ギャスパー・ウリネル)もいた。3年後、マチルドの元に手紙が届く。手紙の主は戦場でマネクに会ったという元伍長のエスペランザ(ジェン=ピエール・ベッケル)。エスペランザは戦場で見た5人の最後の様子を話し、遺品をマチルドに渡す。マネクの生存を信じるマチルドはパリへ出かけ、探偵に真相解明を依頼するとともに、自ら関係者を訪ねて歩くことにする。
マチルドは幼い頃、小児麻痺にかかり、左足が不自由な設定。マネクに何かあれば分かるという直感も持っている。ジュネらしいのはこのまるで「アメリ」のようなマチルドのキャラクターと周囲の人間たちのエピソードだ。親代わりの叔父夫婦や郵便配達、探偵などがユーモラスに描かれる。しかし、映画の基調は悲惨な戦場シーンをはじめ、重いものである。悲惨で理不尽な戦場の描写が映画に落とす影は大きいのだが、それが反戦への訴えになっているかというとそういう部分が強調されるわけでもない。部分的に優れたシーンがありながら、まとめ方は平凡な映画だと思う。
行方不明となった兵士の妻役で中盤にジョディ・フォスターが出てくる。短いシーンだが、印象は強く、さすがという演技を見せた。この役が最後に関係してくるのかと思ったが、それはなかった。もったいないような使い方ではある。音楽はデヴィッド・リンチ映画の常連であるアンジェロ・バダラメンティが担当し、リンチ映画とは異なった正統的なメロディを聴かせる。製作予算の35%がアメリカ資本とのことで、今年のアカデミー賞では美術、撮影の2部門にノミネートされた。
2007年03月18日 [Sun]
■ [MOVIE] 「不都合な真実」
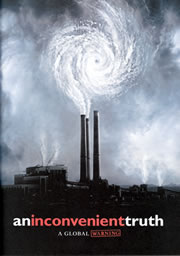 「省エネルギーの電化製品や電球に交換しましょう」「リサイクル製品を積極的に利用しましょう」。アカデミー主題歌賞(歌曲賞)を受賞したメリッサ・エスリッジの「I Need to Wake Up」が流れるエンドクレジットにそうしたメッセージが表示される。「これは政治ではなく、道徳問題なんです。強い意志を持って今こそ行動しましょう」。アカデミー長編ドキュメンタリー賞の受賞スピーチでアル・ゴアは映画の中の主張を再び繰り返すコメントをした。そうだその通りにしなくては、という気分になってくる映画である。世界各地で1000回以上行ってきたという講演を中心に組み立てたこの作品、決して映画としての技術は優れてはいないが、昨今の異常気象を見ていると、メッセージにあふれたこの映画の存在は大きい。ゴアの真摯な姿勢も尊敬すべきものであり、価値のある作品だと思う。
「省エネルギーの電化製品や電球に交換しましょう」「リサイクル製品を積極的に利用しましょう」。アカデミー主題歌賞(歌曲賞)を受賞したメリッサ・エスリッジの「I Need to Wake Up」が流れるエンドクレジットにそうしたメッセージが表示される。「これは政治ではなく、道徳問題なんです。強い意志を持って今こそ行動しましょう」。アカデミー長編ドキュメンタリー賞の受賞スピーチでアル・ゴアは映画の中の主張を再び繰り返すコメントをした。そうだその通りにしなくては、という気分になってくる映画である。世界各地で1000回以上行ってきたという講演を中心に組み立てたこの作品、決して映画としての技術は優れてはいないが、昨今の異常気象を見ていると、メッセージにあふれたこの映画の存在は大きい。ゴアの真摯な姿勢も尊敬すべきものであり、価値のある作品だと思う。
地球温暖化の影響でグリーンランドなど陸地の氷河が溶けて海に流入すると、海流が止まり、暖流がなくなることで極地付近の気温が低下する。ローランド・エメリッヒ「デイ・アフター・トゥモロー」(2004年)で(極端に)描かれたことをゴアは講演の中で分かりやすく説明する。極地の氷が溶けると、海水面は6メートル上がり、世界各地で多大な被害も引き起こす。巨大な台風やハリケーン、大雨によって毎年のように被害が起きているから、ゴアのこの説明には説得力がある。そのすべての原因は人間が経済活動によって出している温室効果ガス。それは急激に増えている。これを減らすのは「モラルの問題だ」というのがゴアの主張である。
地球温暖化には懐疑的な意見も含めてさまざまな説が存在するようだ。30年以上にわたって地球温暖化防止に関する活動をしてきたゴアの主張は危機感の強いものだが、ウィキペディアによれば、海水面の上昇は6メートルではなく、「西暦2100年までに30cmから1m」という計算もあるらしい。この映画に描かれたことがすべて真実かどうか、データの解釈が正確かどうかは僕にはよく分からない。「ジュラシック・パーク」の作家マイクル・クライトンでさえ、「恐怖の存在」で地球温暖化説を否定している(これには批判が多い)。
だが、人間が行う活動によって温暖化に限らず、地球環境が害されていることは否定できないだろう。「不都合な真実」がすべて真実であるとかたくなに信じてしまうことは宗教と同じになってしまって良くないと思うが、ゴアが言っている一人ひとりがモラルの意識を持って生活しようという主張は歓迎すべきことだ。ただ、個人的にはモラル以上に政治の問題も多く含まれていると思う。ゴアが選挙で敗れたブッシュ大統領が富裕層の方しか見ていないことは「華氏911」(2004年)でマイケル・ムーアが痛烈に描いていたが、この映画に足りないものがあるとすれば、ああいう権力に対する批判の鋭さだろう。モラルの問題だけでなく、政治の問題も大きいことをもっと指摘しても良かったのではないかと思う。モラルの問題だけにしてしまうと、温室効果ガスを大量に出している企業への圧力は高まらないのではないか。
2009年03月18日 [Wed]
■ Namazu検索結果の日本語化
さくらインターネットのサーバーがバージョンアップして以来、Namazuの検索結果が英語になった(Result: Total 869 documents matching your query.などと表示される)。昨日書いたようにサーバーにデフォルトでNamazuがインストールされていることが影響しているらしい。ユーザー領域にインストールしたので直るかと思ったら直らない。Namazu MLの過去のメールを検索したら、[Namazu-users-ja 520] Re: Namazuの検索結果を日本語にしたいのですが。というスレッドがあった。
で、/home/cinema1987/local/bin/にあるnamazurcとnamazu.cgiがあるフォルダの.namazurcのLangにja_JP.eucJPを設定したら、日本語になった。今まではnamazurcの方にはJaとだけ書いていた。
新しいサーバーの情報を見てみたら、File-MMagicはちゃんと入っていた。おまけにMeCabもperlモジュールが入ってる。これなら、KAKASIの代わりにMeCabを使えばいいわけで、Namazuのインストールは随分楽になる。configureの後、インストールすればいいのだった。
