映画とネットのDIARY(tDiary版)
検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。
【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2004年09月23日 [Thu]
■ 松下、Blu-ray再生専用機を2006年に投入へ
価格が10万円以下というのが驚きだし、「Sony Pictures Entertainmentや(先日ソニーが買収した)Metro-Goldwyn-Mayer Studios(MGM)がHD DVDを採用するかは疑問だ」という言葉にも説得力がある。ということはBlu-rayが有利なのだろう。互換性は維持されるだろうが、今の片面2層DVDの運命も先が見えてきた感じ。2年先に再生専用機が発売されるのなら、今のDVD、あまり買わない方がいいのかも。
■ イチロー、あと「10」
6打数4安打。敬遠が一つあるので7回も打席が回ってきたことになる。普通の2試合分ですね。これほど打席が多いと楽だなあ。残り10試合だが、今のペースなら、あと3試合で記録達成の可能性もある。
■ みんなの光プロジェクト
不要なメールを削除していたら、@niftyからのお知らせが目に入った。9月1日から光ファイバーコースの会員はメール、ホームページとも容量が20MBから100MBに増えるという連絡。しかも家族用IDが2つから4つに増えるという。メールにはちゃんと目を通さなくちゃいけませんね。それにしても、全然容量が変わっていないぞと思ったら、申し込みが必要なわけですね。で、さっそく申し込む。
少し残念なのは、実は「シネマ1987online」、家内のIDで取得している。だからここが100MBになるわけではなく、20MBのまま。増えたのは僕のIDで取得したホームページスペース。ここには現在、テスト的なCGIを置いているだけでリンクも公開もしていない。ここを増やしてもあまり意味はないんですけど、そのうち何かに使うかもしれないし、狭いより広いのに越したことはない。
家族用IDのホームページとメールも増やしてくれるとうれしいんですが、さくらインターネットには3GBもあって、まだ100MB余りしか使っていないのだから、もういらないや。家族用ID4つということは、うちの家族はこれで事足ります。まだ子どもはメールなんて使わないし、家内も使っていないけど。家内はたぶんメールアドレスさえ覚えていないはず。それによく考えてみたら、さくらインターネットでメールアドレスは無制限に作れるのだった。そうなると、あまりメリットはないなあ。
2005年09月23日 [Fri]
■ [MOVIE] 「チャーリーとチョコレート工場」
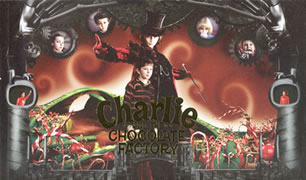 ロアルド・ダール原作の童話「チョコレート工場の秘密」をティム・バートン監督が映画化。前作の「ビッグ・フィッシュ」に続いて、家族愛を歌い上げるファンタジーである。3連休の初日のためか劇場は満員。200席ほどの映画館だが、左端の上から2番目と1番目の並びの席に家族5人で座る。上の方は冷房の利きが悪く、暑かった。睡眠不足のためもあって、途中でウトウト。映画がつまらなかったわけではないが、同じ家族愛ならば、「シンデレラマン」の後では少し分が悪いのは確かだ。いつものように快調なダニー・エルフマンの音楽とジョニー・デップの演技を楽しんだけれど、話自体にちょっと物足りない思いも残った。
ロアルド・ダール原作の童話「チョコレート工場の秘密」をティム・バートン監督が映画化。前作の「ビッグ・フィッシュ」に続いて、家族愛を歌い上げるファンタジーである。3連休の初日のためか劇場は満員。200席ほどの映画館だが、左端の上から2番目と1番目の並びの席に家族5人で座る。上の方は冷房の利きが悪く、暑かった。睡眠不足のためもあって、途中でウトウト。映画がつまらなかったわけではないが、同じ家族愛ならば、「シンデレラマン」の後では少し分が悪いのは確かだ。いつものように快調なダニー・エルフマンの音楽とジョニー・デップの演技を楽しんだけれど、話自体にちょっと物足りない思いも残った。
映画のタッチはバートンらしいブラックな趣味にあふれている。主人公のチャーリー・バケット(「ネバーランド」のフレディ・ハイモア)は斜めに傾いた家に両親とその両方の祖父母の計7人で住む。食事はいつもキャベツのスープ。4人の祖父母は1つのベッドに寝たきり。父親は歯磨きの工場でキャップを閉める仕事をしている。貧しい暮らしだが、チャーリーは家族が大好きだ。街にはウィリー・ウォンカ(ジョニー・デップ)というチョコレート作りの天才が建てた大きな工場がある。チャーリー自身がチョコを口にするのは年に1回、誕生日の時だけである。ウォンカのチョコレートは世界中に出荷され、人気を集めている。工場はスパイを防ぐため、15年前に従業員をやめさせたが、なぜか今も生産は続いており、工場の中がどうなっているのか、人々は興味津々。ある日、ウォンカが子ども5人を工場に招待すると発表する。その招待券はチョコに入った黄金のチケット。チャーリーが誕生日にもらったチョコには黄金のチケットはなかった。祖父のなけなしのへそくりで買ったチョコにもチケットはなかったが、チャーリーは道ばたで拾った10ドル札で買ったチョコでチケットを手に入れる。
家族思いのチャーリーは、500ドルで買いたいという人がいるので家の暮らしのためにもチケットを売る、という(これは原作にはない)。それに対する祖父のセリフがいい。「お金は印刷されてたくさん出回っている。そのチケットは5枚しかない。それをお金に換えるほどお前はトンマか」。チョコレート工場に招待された5人の子どものうち、チャーリーを除く4人はいずれもいけ好かないガキ。高慢ちきな少女であったり、わがまま娘だったり、ガツガツしたデブの少年だったり、知能は高いが人をバカにしたような少年であったりする。その4人は予想通りの仕打ちを受けることになる。
工場内部の描写がおかしくていい。チョコを作っている多数のウンパ・ルンパ族やリスたちの場面には大笑い。特にリス。リスたちはクルミの選別を手伝っており、中身のないクルミは捨てている。リスを捕まえようとした少女の頭をコンコンとたたいて、哀れ、少女は不良品と判断されてしまうのだ。こういうキャラクター、どこかで見たなあと思うのだが、なかなか思い出せないのがもどかしい。アメリカのアニメに時々出てくるようなギャグではある。
ブラックな味わいはあっても、最終的には心温まる話に着地する。それがバートンらしくないというのはもう間違いで、バートンの興味はそういう部分に移ってきているのだろう。気になったのはチャーリーが拾ったお金でチケットを手に入れること。これは何か後を引くのではないかと思ったが、そういう部分はなかった。子どもは「『マダガスカル』の方が面白かった」との感想。そんなはずはないんだがなあ。字幕を読むのに精いっぱいだったのか。
2006年09月23日 [Sat]
■ 「惑星大怪獣ネガドン」(DVD)
 というわけで見る。怪獣映画マニアの作った昭和の怪獣映画風3DCG。監督の粟津順は1974年生まれで、学生時代に「ガメラ2 レギオン襲来」を見てショックを受け、怪獣映画の本格的なファンになったのだという。続く「ガメラ3 邪神覚醒」がCG作家を志すきっかけになったそうだ。「ネガドン」の怪獣が何となくイリスを思わせるのはそれが影響しているのかもしれない。
というわけで見る。怪獣映画マニアの作った昭和の怪獣映画風3DCG。監督の粟津順は1974年生まれで、学生時代に「ガメラ2 レギオン襲来」を見てショックを受け、怪獣映画の本格的なファンになったのだという。続く「ガメラ3 邪神覚醒」がCG作家を志すきっかけになったそうだ。「ネガドン」の怪獣が何となくイリスを思わせるのはそれが影響しているのかもしれない。
ストーリーは簡単で、火星のテラフォーミングが進む昭和百年が舞台。火星の地下から現れた怪獣が地球に落ちてくる。それを工事用ロボットのMI-6(ミロクと読む)が迎え撃つ。MI-6を操縦する中年の研究者は過去にロボットの事故で一人娘を亡くしているという設定。それだけの物語である。25分の短編だからこのストーリーで良いのだろうが、長編を作るなら、物語の工夫はもっと必要になってくるだろう。話は怪獣映画以上のものではない。SFの分かる脚本家が力を貸せば、もっと充実したものになると思う。
2年4カ月かけて一人で作った作品なので、良くできているところもあれば、そうでないところもあるが、技術的には水準以上と思う。可能性を感じさせる。人間のCGがあまりうまくないのはアメリカのピクサーあたりもそうだから仕方がない。うまくいかないのなら実写を使えばいいことで、粟津順には将来的に役者を使い、CGを組み合わせた怪獣映画を撮って欲しいところだ。
小説を書くように映像を作れる時代になったと、粟津順はDVDに収録されたインタビューで語っている。1人で作る方が良いのか、共同作業が良いのかは難しい問題ではある。監督に向く人も向かない人もいるだろうから、個人でうまくいった人が共同作業でも素晴らしい作品を作れるとは限らない。それでもこの技術を個人の枠内に収めておくのはもったいないと思う。より充実できる部分が多くあるからこそ、可能性も感じるのである。
■ [MOVIE] 「ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟」
 ウルトラマンシリーズ生誕40周年記念作品。出てくるのは初代ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン(今はウルトラマンジャックと呼ばれる)、ウルトラマンエース。どれもリアルタイムに見ていたので、黒部進、森次晃嗣、団時朗、高峰圭二が出てくると、懐かしさがこみ上げてくる。そういうノスタルジックというか40年の歴史の重みを一番感じさせるのはエンドロールで、桜井浩子やひし美ゆり子、星光子まで顔を出すのが何というか感涙ものである。桜井浩子はウルトラマンの後、実相寺昭雄の映画に出ていたし、ひし美ゆり子も東映映画などに出ていた(というか桜井浩子はウルトラマン以前からかなりの映画出演歴がある)。
ウルトラマンシリーズ生誕40周年記念作品。出てくるのは初代ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマン(今はウルトラマンジャックと呼ばれる)、ウルトラマンエース。どれもリアルタイムに見ていたので、黒部進、森次晃嗣、団時朗、高峰圭二が出てくると、懐かしさがこみ上げてくる。そういうノスタルジックというか40年の歴史の重みを一番感じさせるのはエンドロールで、桜井浩子やひし美ゆり子、星光子まで顔を出すのが何というか感涙ものである。桜井浩子はウルトラマンの後、実相寺昭雄の映画に出ていたし、ひし美ゆり子も東映映画などに出ていた(というか桜井浩子はウルトラマン以前からかなりの映画出演歴がある)。
メビウスの物語にウルトラ兄弟の面々を絡ませた展開は悪くないのだが、怪獣に襲われて心を閉ざした少年のエピソードに魅力を感じない。作劇としてうまくないのだ。加えて、GUYSの戦闘機のいかにもオモチャ然とした造型および質感は僕には見ていく上での障害でしかなかった。板野サーカスと言われるCG監督板野一郎のCGも取り立てて騒ぐ出来ではない。小中和哉監督作品としては大人の観賞を意識して作った前作「ULTRAMAN」(2004年)の方が面白く、今回の映画は子供向けストーリーの域を出ていないのが惜しい。マニアは喜ぶだろうが、ウルトラマン世代向けなのは懐かしさだけなのである。
20年前、異次元超人ヤプールの怨念で生まれた究極超獣Uキラーザウルスをウルトラ兄弟は協力して神戸沖に封印する。パワーを使い切ってしまったために4兄弟は変身能力を失い、以後は市井の民間人として暮らしていた。そして現在、GUYSのヒビノミライ(五十嵐隼士)は神戸に異変を感じて一人出動する。テンペラー星人、ガッツ星人、ナックル星人、ザラブ星人の宇宙人連合がUキラーザウルスを復活させようとしていたのだ。ミライは現れたテンペラー星人をメビウスに変身して倒すが、その戦いで宇宙人連合に能力を知られ、倒されて十字架に架けられてしまう。ウルトラ兄弟はメビウスを救うために死を覚悟して変身する。しかし、宇宙人連合の狙いは4兄弟の方にあった。兄弟のエネルギーでUキラーザウルスを復活させたのだ。
これが本筋でサイドストーリーとして描かれるのが、天才科学者ジングウジアヤ(いとうあいこ)の弟で怪獣に襲われて心を閉ざしたタカト(田中碧海)の話。タカトはGUYSとウルトラマンメビウスにあこがれていたが、一緒にいた愛犬を救おうとしなかった自分を責めていた。この話がどうもテレビシリーズレベルの話である。子供を意識したのだろうが、全体の流れから言えば不要としか思えない。クライマックスは巨大化したUキラーザウルスとウルトラ兄弟の戦いをCGを駆使して描く。ここはそれなりに見応えはあるものの、これがこの映画の魅力かと言えば、そうでもないだろう。子供なんか意識しなくていいから、ガチガチの4兄弟の話にした方が良かったように思う。
気になったのはミニチュアの神戸の街並みに登場する着ぐるみ怪獣たちのリアリティ欠如。平成ガメラシリーズも着ぐるみだったのに、あれはどうしてあんなにリアリティを持ち得たのか。たぶんドラマとエモーションががっちり組み合わさっていたからだろうと思う。ウルトラマンシリーズでも「ウルトラセブン」が名作だったのは脚本家・金城哲夫の存在が大きかった(どうでもいいが、この夏、石垣島に行った際、金城哲夫作品のDVDボックスのテレビCMが盛んに流れていた。沖縄では金城哲夫の名前でDVDが売れるのか)。映画の中にも引用されるキングジョーとの戦いや最終話のドラマティックさがこの映画にも必要なのだろう。小中和哉、次もウルトラマンを作るなら、脚本にもっと力を入れて欲しいと思う。
