映画とネットのDIARY(tDiary版)
検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。
【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2004年11月15日 [Mon]
■ 著作権フリー映画
PD CLASSICという会社からメール。懐かしのDVDを380円で販売しているそうだ。著作権が切れてパブリック・ドメインになった映画ばかり。380円という価格は魅力ではあるが、疑問なのはどこからフィルムを入手しているかということ。JR東日本のキオスクでも販売しているそうだから、信用がないわけではないが、気になるところ。 Googleで検索してみると、フジサンケイビジネスアイの記事(Googleのキャッシュ)にこうあった。ピーディー・クラシックは、フィルムとして保管されているパブリックドメイン作品を持っている米国企業から映像を買い、DVD化して発売する。デジタル技術を使って、フィルムの汚れや傷を修正し、日本語字幕を付けて収録している。
なるほど。アメリカにはパブリック・ドメインの映画を管理している会社があるのか。それにしてもこの会社のページ、「ページが見つかりません」が頻発して信用度を落としてますね。おまけにメールはCCで送られているし。ちょっと気を遣った方がいいと思うぞ。
■ [MOVIE] 「コラテラル」
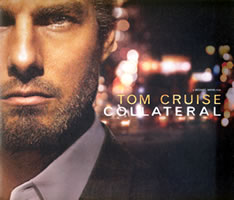 12年間タクシーの運転手をしているマックス(ジェイミー・フォックス)には夢がある。リムジンの会社を持つこと。タクシー運転手は本人にしてみれば、仮の仕事である。そんなマックスを見透かしたように殺し屋のヴィンセント(トム・クルーズ)が言う。「みんないつかは自分の夢が実現すると思ってる。しかし、何もしない。夢をどこかに置いて、テレビをボーっと見ている。そしてある日、鏡を見て自分が年を取ったことに気づくのさ」。
12年間タクシーの運転手をしているマックス(ジェイミー・フォックス)には夢がある。リムジンの会社を持つこと。タクシー運転手は本人にしてみれば、仮の仕事である。そんなマックスを見透かしたように殺し屋のヴィンセント(トム・クルーズ)が言う。「みんないつかは自分の夢が実現すると思ってる。しかし、何もしない。夢をどこかに置いて、テレビをボーっと見ている。そしてある日、鏡を見て自分が年を取ったことに気づくのさ」。
これと対をなすのが序盤にある女性検事アニー(ジェイダ・ピンケット=スミス)との会話で、翌日の公判を控えてナーバスになっているアニーにマックスは休養を取るよう勧める。自分は仕事中でもボラボラ島の写真を5分間見ることで休息していると言い、「これが必要なのはあんただ」と写真を渡す。そしてアニーは自分の名刺を渡すのだ(2人に交流が芽生えるこのシーンを見れば、クライマックスの予想は付く)。事件の巻き添え(コラテラル)になったタクシー運転手という本筋の話よりも印象に残るのはそんなセリフで、脚本のスチュアート・ビーティー、サスペンスとは別の意味でなかなかうまいと思う。マイケル・マン監督の映画としては特に出来がいいわけではないが、演出は的確であり、ひと味違ったサスペンス映画になっている。
マックスはアニーを降ろした後、同じビルの前でヴィンセントを乗せる。予測した通りの時間でヴィンセントを目的地まで送り届けると、マックスの腕を見込んだのか、ヴィンセントは600ドルで今夜行く数カ所への運転を依頼する。マックスが一休みしていたところ、ビルの窓から車の屋根に死体が落ちてくる。死体はヴィンセントが殺した男。ヴィンセントは殺し屋で今夜5人を始末するという。脅されたマックスは男の死体をトランクに入れ、次の目的地に向かう。死んだ男は麻薬組織の一員で、裁判の証人だった。男が消えたことで麻薬捜査官のファニング(マーク・ラファロ)など警察も捜査を開始する。ヴィンセントが3人目を殺したところで、マックスはヴィンセントの鞄を奪い、道路に投げ捨てる。中には標的の資料が入っていた。ヴィンセントは組織のボス、フェリックスに会い、標的の資料をもらうよう強要する。
タクシー運転手が主人公の映画と言えば、マーティン・スコセッシ「タクシー・ドライバー」がある。あの映画がニューヨークの風俗をつぶさに映し出したほど、ロサンゼルスの街がよく描かれているとはいえないのがちょっと不満な点。これは狙いが違うのだから仕方ないが、平凡な運転手だったマックスの変化も明確には描かれないのが弱いところか。クライマックスは5人目の殺しを阻止しようとするマックスとヴィンセントの対決になる。いくらヴィンセントがけがをしていたとはいっても、マックスに勝てる理由は見あたらないのも弱い。しかし、ジェームス・ニュートン・ハワードの音楽とディオン・ビーブの撮影はともにレベルが高く、映画に貢献している。
凄腕のタフな殺し屋を演じるトム・クルーズは、白髪交じりの髪に無精ひげのメイクでうまく役にはまっている。美男俳優が殺し屋を演じるのはアラン・ドロンを持ち出すまでもなく、かつては普通のことだった。冒頭、ヴィンセントが降り立つ空港の場面に「スナッチ」「ザ・ワン」のジェイソン・ステイサムが出てくる。ヴィンセントにぶつかって鞄を渡す男の役でパンフレットには名前が記載されていない(この映画のパンフはまったく詳しくない)。ゲスト出演か。
2005年11月15日 [Tue]
■ ヤフー、送信メールにも迷惑メールフィルター適用
これで少しはYahoo!発のスパムが減るだろう。もっとも、なりすましメールも多いそうなので、この記事でも「半減」と書いてありますがね。hotmailも送信側のフィルタを導入してほしい。
■ [MOVIE] 「イン・ハー・シューズ」
 現在の不幸の要因が過去にあるというのはミステリではよくある設定だ。この映画の姉妹は不幸というほどではないが、それぞれに日常生活に問題を抱えている。姉のローズ(トニ・コレット)は弁護士だが、小太りで(とは見えないが)容姿にコンプレックスを持っている。妹のマギー(キャメロン・ディアス)は容姿・スタイルとも抜群だが、難読症で自分は頭が悪いと思っている。母親は2人が子供の時に交通事故死した。その秘密がクライマックスに明らかになる。そして仲違いしていた姉妹はかつてのような姉妹の絆を取り戻す。簡単に言えば、そういう話なのだが、この映画の良さはそうしたプロットにあるのではなく、それぞれの問題を克服していく姉妹の姿にある。マギーがフロリダの老人ホームで盲目の元大学教授の指導を受けて、E・E・カミングスの詩を読み、ゆっくりと難読症を克服していく描写や、あの「ロッキー」にも登場したフィラデルフィア美術館の階段をローズが犬と一緒に駆け上がるシーンなどは感動的だ。
現在の不幸の要因が過去にあるというのはミステリではよくある設定だ。この映画の姉妹は不幸というほどではないが、それぞれに日常生活に問題を抱えている。姉のローズ(トニ・コレット)は弁護士だが、小太りで(とは見えないが)容姿にコンプレックスを持っている。妹のマギー(キャメロン・ディアス)は容姿・スタイルとも抜群だが、難読症で自分は頭が悪いと思っている。母親は2人が子供の時に交通事故死した。その秘密がクライマックスに明らかになる。そして仲違いしていた姉妹はかつてのような姉妹の絆を取り戻す。簡単に言えば、そういう話なのだが、この映画の良さはそうしたプロットにあるのではなく、それぞれの問題を克服していく姉妹の姿にある。マギーがフロリダの老人ホームで盲目の元大学教授の指導を受けて、E・E・カミングスの詩を読み、ゆっくりと難読症を克服していく描写や、あの「ロッキー」にも登場したフィラデルフィア美術館の階段をローズが犬と一緒に駆け上がるシーンなどは感動的だ。
ジェニファー・ウェイナーの原作を脚本化したスザンナ・グラント(「エリン・ブロコビッチ」)は女性らしい視点で詳細に姉妹の自己実現の様子を綴っている。まるで娯楽映画には向かないような題材にもかかわらず、手堅くまとめたカーティス・ハンソンの演出も見事。しかし、何よりもこの映画はキャメロン・ディアスに尽きる。マイナーからメジャー作品まで幅広い映画に出演してきたディアスはこの映画で奥行きの深い演技を見せており、本当に演技派と呼べる女優になったのだと思う。
舞台はフィラデルフィア。マギーは高校の同窓会で酔っぱらい、元々仲の悪かった継母から実家を追い出されて姉のローズのアパートに転がり込む。弁護士事務所に勤めるローズはちょうど上司のジム(リチャード・バージ)とつきあい始めたところだった。難読症で計算もできないマギーは就職しても長続きしない。いつまでたっても経済的に自立しないマギーにローズはいらだちを募らせる。しかも、ふとしたことからマギーはジムとベッドイン。そこに帰ってきたローズは怒りを爆発させ、マギーを追い出す。仕方なく実家に帰ったマギーはそこで死んだと思っていた母方の祖母エラ(シャーリー・マクレーン)がフロリダで健在なのを知る。マギーはフロリダの老人ホームでエラと暮らすことになるが、初めは歓迎していたエラも遊び暮らすマギーにホームの仕事を手伝うよう命じる。一方、ローズは気まずくなった弁護士事務所を辞め、犬の散歩の仕事を始める。ある日、街角で事務所の同僚だったサイモン(マーク・ファイアスタイン)と偶然会い、食事に誘われる。サイモンは以前からローズに好意を持っていたのだ。
問題を抱えているのは姉妹だけではない。祖母は娘に対して過剰な保護をしていたし、父親は妻の死後、祖母から娘への手紙を隠し続けてきた。継母は姉妹を(特にマギーを)嫌っている。さまざまな要素が入り組んだ話でありながら、笑いを織り交ぜて緩急自在にてきぱきと整理していくハンソンの演出は大したものだと思う。2時間13分、少し冗長に思える部分もあるのだが、泣かせよう感動させようなどという安易な意図が微塵もないところが最大の美点。過剰さを廃したこういう演出は好ましいし、洗練されていると思う。
ディアスはスタイルの良さを見せつける序盤から中盤までもいいのだが、それ以降も的確に演技をこなしている。ラスト、新婚旅行に旅立つ姉を見送った後、ステップを弾ませて結婚パーティの踊りの輪に加わっていくハッピーな終わり方がとても良かった。
2007年11月15日 [Thu]
■ wizpy優待販売
Turbolinuxからメール。ターボリナックスのユーザーに通常29800円のwizpyを9800円で販売するという。おお、それは安い、買ってしまおうかと一瞬思ったが、そもそもwizpyが何なのかを知らない。Turbolinuxのサイトも良くない。きちんと説明して欲しい。ITmedia +Dのちっちゃなボディに大きな期待――「wizpy」は本当に“すごい”のかの方がよく分かった。要するに「マルチメディアプレーヤー機能を備えた、Turbolinuxブートイメージ入りUSBメモリ」。
メールの説明を引用すると、「ポータビリティに優れた50gほどの小さなデバイスで自分の PCソフトウェア環境一式を特定のパソコンに縛られることなく自由に携帯する」ことができるというわけ。音楽プレーヤーとしても使えるし、パソコンのUSBに挿して起動すれば、Turbolinuxを使える。
が、誰がTurbolinuxを使うんだ。携帯メディアプレイヤーを使うような層はまずLinuxなんて使わない(知らない)。社内のしゃれたSEが持ち歩いていて、パソコンが起動しなくなったら、これを挿してちゃちゃっと修理するとかの場面は、まずSEがTurboなんて使うはずがないというところで挫折する。そういう用途にはKNOPPIXのCDがあればすむこと。元々のTurbolinuxユーザーなら使うかもしれないが、かなり数は限られるだろう。
これでは大きく売れるわけはない。だいたい2月に発売して今ごろ優待販売とは売れていない証拠だろう。面白い試みとは思うけれど、Linuxユーザーを超えて一般にアピールする力が根本的に足りないと思う。
