映画とネットのDIARY(tDiary版)
検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。
【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2005年07月08日 [Fri]
■ 「キング・コング」予告編
ピーター・ジャクソンによる3度目の映画化。アメリカでは12月14日に公開される。と思ったら、世界同時公開とのこと。「宇宙戦争」と同じく水曜日封切りになるようだ。
劇場で既に予告編が流れているが、劇場版ではピーター・ジャクソン自身(とは思えないほど痩せている。本当に本物か?)が前ふりをする。主演女優(つまり、フェイ・レイの役)はナオミ・ワッツだったのか。年齢的には少し苦しいが、きれいだからいいか。ほかに「スクール・オブ・ロック」のジャック・ブラック、「戦場のピアニスト」のエイドリアン・ブロディが出ている。キング・コングの動きは「マイティ・ジョー」を思わせるな。
2006年07月08日 [Sat]
■ [MOVIE] 「カーズ」
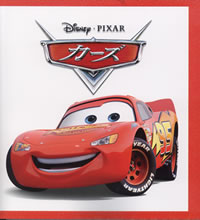 ピクサーの3DCGアニメだが、ジョン・ラセターの監督・脚本作としては「トイ・ストーリー2」以来7年ぶり。新人レースカーのライトニング・マックイーンがラジエーター・スプリングスという寂れた町で人間的な成長を果たす姿を描く。もう端的にスピード重視、最短距離重視ではなく、ちょっと寄り道してもいいじゃないか、という映画。自分の勝利よりも人間的な在り方が大事という当たり前のことを当たり前に描いた映画である。
ピクサーの3DCGアニメだが、ジョン・ラセターの監督・脚本作としては「トイ・ストーリー2」以来7年ぶり。新人レースカーのライトニング・マックイーンがラジエーター・スプリングスという寂れた町で人間的な成長を果たす姿を描く。もう端的にスピード重視、最短距離重視ではなく、ちょっと寄り道してもいいじゃないか、という映画。自分の勝利よりも人間的な在り方が大事という当たり前のことを当たり前に描いた映画である。
脚本もきちんと定跡をふまえた展開になっている。そういうストレートな映画は最近少ないし、「俺、お前を選んで良かったよ」「何に?」「親友!」という人のいいレッカー車のメーターとライトニング・マックイーンの会話などはアニメでなければもはや成立しないのではないかと思う。子供を連れて見に行った大人も楽しめる作品で、大人の方が作品の深い部分には共感できるだろう。驚くのはCGの技術で、最近のピクサーアニメの中でもピカイチの出来。車のスピード感あふれる走りや光沢、動きに加えて、レース場の観客席の大量の車の細かい描写に感心した。音響効果もエンジン音、走行音なども細かい。丁寧に作られたファミリー映画の手本みたいな作品と思う。
自動車レースのピストン・カップでライトニング・マックイーンは新人初のチャンピオンとなることを目指していた。ライバルは今シーズン限りでの引退を決めているキングと万年2位のチック・ヒックス。マックイーンはトップに躍り出るが、ピットインで時間節約のためガソリン補給だけでタイヤ交換をしなかったため、タイヤが破裂。ゴール直前でキングとヒックスに追いつかれ、3台が同時にゴールして、あらためてカリフォルニアで再レースをすることになる。運搬用トラックのマックでカリフォルニアに向かったマックイーンは居眠りしたマックから落ちてはぐれてしまう。マックイーンはラジエーター・スプリングスという寂れた町にたどり着くが、ひょんなことから道路を壊してしまい、警察に捕まり、道路補修を命じられる。
ラジエーター・スプリングスはかつては栄えた町だが、近くに高速道路ができたために訪れる人もなくなり、地図からも名前が消えてしまった。都会での弁護士生活に疲れ、ラジエーター・スプリングスに来たサリーは言う。「かつての道路は今のように地形を無視したまっすぐなものじゃなくて、地形に沿って走っていた。最短距離を移動するものじゃなくて、移動を楽しむものだったのよ」。急いで生きる人生を見つめ直す。効率よりも人間性。そういうニュアンスの言葉が映画には散りばめられていて、シンプルな主張になっている。擬人化した車たちによって語られる寓話と言えようか。ラセターはそれを無理なく語っている。
僕が見たのは日本語吹き替え版。かつての名レーサーで、心に傷を持つドック・ハドソンの声をポール・ニューマンが演じているそうで、これはどうしても字幕版が見たくなる。
2008年07月08日 [Tue]
■ 日本のクルマはスピンしやすい!? 〜ボッシュの「ESC」記者説明会から
ESC(エレクトリック・スタビリティ・コントロール)の普及度が日本はまだまだ低い。「コンパクトタイプ(トヨタ・カローラなど)だと25%、スモールタイプ(ホンダ・フィットなど)になると5%まで落ち込む」とのこと。ESCはいわゆる横滑り防止装置だが、名称がESPとかVDCとか各社でバラバラな状態。ABSのように統一しないと認知度は高まらないのではないか。
元々、この装置、Aクラスがエルクテストで転倒しやすいとの結果が出た後、メルセデスが普及価格帯のAクラスにも搭載するようになったそうだ。普及価格帯のクルマに装備しないと意味が薄い。ワールド・カー・オブ・ザ・イヤーのデミオの日本仕様にはこれ、オプションでも付けられない。ユーザーの認知の低さを反映した結果なのだろう。安全装置付けるよりは安く売れ、というのが通用するのだ。
2009年07月08日 [Wed]
■ [MOVIE] 「ディア・ドクター」「ウルトラミラクルラブストーリー」
2泊3日の出張でぐったりなので、どちらも短い感想にとどめておく。長い感想はSorry, Wrong Accessの方に書く(予定)。
まず「ディア・ドクター」。小説版のアナザー・ストーリー「きのうの神さま」を読んでいたので、これは僻地医療に関する映画だろうという先入観があった。その観点から見れば、困ったことに主人公の設定がマイナスにしか作用しない。西川美和は「赤ひげ」風になるのを避けてこういう設定にしたのだろうが、これでは医療の問題は深く言及しようがないのだ。なぜこんな設定にしたのか。キネ旬7月下旬号の桂千穂の批評を読んで、その疑問は氷解した。
西川美和は前作「ゆれる」で高く評価された。「すると、誰もが映画監督としての技術や識見の持ち主と信じて疑わなくなった」そうだ。それに対する疑問の提示がこの映画なのだ。「私自身がそうであるように、何かに“なりすまして”生きている感覚は誰しもあるだろう。それで世の中が辛うじて成り立っている部分もあるはずだ。贋物という言葉が孕むそんな曖昧さを物語として面白く見せられないかなというのが企画の出発点になった」。そう言われれば、よく分かる。しかし、それならば、僻地医療を舞台にする意味があるのか。せっかく僻地医療の現状を取材したのにそういう話にしてしまっては意味が薄いように思う。
西川美和に社会派を期待する方が間違いなのかもしれない。その問題は小説に結実させたのだから、映画はこれで良いのかもしれない。気胸患者を治療する場面の緊迫感をはじめ映画の描写には文句の付けようがないし、笑福亭鶴瓶、余貴美子らの演技にも納得させられた。井川遥も良かった。しかし、やっぱり、せっかく取材したのにもったいないという思いが残る。主人公の若い頃を描いてまったく隙がない小説版「ディア・ドクター」の域には到底達していないのは残念。本物偽物の話なら小説版の描写を取り入れた方が奥行きは出たと思う。看護師役の余貴美子にしても小説版の背景が描かれていれば、なぜ離婚したのか、なぜあんなに有能なのかの説得力も増しただろう。
「ウルトラミラクルラブストーリー」はキネ旬で「“天才監督候補”横浜聡子」という特集が組まれたのでそれなりに期待した。確かに終盤に登場する人を食ったような描写と展開には唖然呆然だった。が、それだけのことでもあった。なぜ主人公がああなるのかの説明が欲しい。その後のストーリーの発展も欲しい。単なるウルトラミラクルでは納得できない。思いつきだけで終わっているとしか思えないのだ。山口雅也「生ける屍の死」ぐらいの説明は欲しいところなのである。
この程度の映画を持ち上げるのは本人のために良くない。と思ったら、映画生活では低い評価が並んでいる。平均評価は59点。いや、そんなに低いとも思わないんですけどね。
西川美和の完璧な演出に比べれば、穴が多いのは否定しようがないが、脚本にもう少し説得力を持たせられるようになれば、真にユニークな存在になると思う。まあ、だからあくまでも今の段階では“候補”なのだろう。
