映画とネットのDIARY(tDiary版)
検索エンジンからのアクセスで、お探しのキーワードが見あたらない場合はNamazuで再検索してみてください。
【映画の感想一覧】 2004年7月以降 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
2006年06月01日 [Thu]
■ ホームページ容量100MB
昨日書いたことは間違い。ホームページのディスク容量を今日確認してみたら、100MBになっていた。Bフレッツ接続だと、親IDも子IDもディスクスペースは100MBになるんだな。これは昨日以上に得した気分。でも考えてみれば、無料のmixiでも100MBあるんだから、これぐらいは当然か。
2006年06月03日 [Sat]
■ Webメール2.0β
広いディスプレイで使うと、普通のメールクライアントみたいで面白いが、ノートの狭い画面では全画面表示にしないと使いにくい。それに反応が遅いのは何とかならないのかと思う。@niftyの場合、普通のWebメールでも遅いが、それ以上に遅い。これは正式版になったら改善されるのだろうか。
2006年06月04日 [Sun]
■ JAF入会
3年ぶりにJAFに入会した。今はクレジットカードでの支払いを選べば、ホームページからすぐに入会でき、仮会員証が印刷できる。入会金2000円、年会費4000円で3年間を選んだ。3年にすると、1000円割引がある。正式の会員証が届くまでには3週間程度かかるそうだ。それまでにトラブルがあったら、仮会員証で大丈夫という。
入会したのは夏の家族旅行がJAFに入っていると、割引があるため。といっても3年分の会費の合計ぐらいの割引にしかならないんですけどね。
2006年06月06日 [Tue]
■ [MOVIE] 「あおげば尊し」
 重松清の原作を市川準監督が映画化。末期ガンの父親を看取る家族と、死体に興味を持つ少年の姿を描く。主人公は小学校の教師。死につつある父親も教師だった。死体に、というよりは死に興味を持つ少年に対して、主人公は死の床にある自分の父親の姿を見せる。父親もそれを受け入れ、少年に対して最後の授業をすることになる。
重松清の原作を市川準監督が映画化。末期ガンの父親を看取る家族と、死体に興味を持つ少年の姿を描く。主人公は小学校の教師。死につつある父親も教師だった。死体に、というよりは死に興味を持つ少年に対して、主人公は死の床にある自分の父親の姿を見せる。父親もそれを受け入れ、少年に対して最後の授業をすることになる。
市川準の他の作品と同じように淡々としたタッチの映画。家庭内で展開される物語なので、見ていて僕はマイク・リーの映画を思い出した。マイク・リーが素人の役者を使うことが多いように、この映画も演技的には未知数のテリー伊藤が初めての主役を務めている。テリー伊藤、静かな演技が意外にうまい。マイク・リーの映画は終盤に劇的で激しい場面を用意することが多いが、この映画はラスト近くまで淡々と進む。もちろん、淡々とした中にキャラクターの造型はしっかり描き込まれていて、だから、ラスト、父親の葬儀の場面で教え子たちが歌う「仰げば尊し」の場面が効果的になる。抑え込まれていた感情が一気に爆発するような効果がここにはある。ドキュメンタリーのような描き方をしていた映画がここだけはっきりとフィクションになり、観客の感情を解放する役割を果たしているのである。それまでのタッチとは著しく異なるので、賛否あるだろうが、ここで泣いたという人も多く、とりあえず大衆性は得ているようだ。テリー伊藤も薬師丸ひろ子も加藤武、麻生美代子もリアルに徹し、ドラマ性を廃した好演をしている。
主人公・光一(テリー伊藤)の父親(加藤武)は末期ガンで余命3カ月と宣告される。「いい思い出を作ってあげてください」との医師の言葉で家族は父親を自宅に連れて帰り、在宅で死を迎えさせようとする。それと同時に描かれるのが光一のクラスの田上康弘(伊藤大翔=名前はひろと、と読む)。康弘はパソコンの授業中に死体のサイトを見ていた。そのこともあって光一はクラスの生徒に父親の姿を見せるが、興味を示したのは康弘だけだった。康宏は死んだ父親の葬儀を覚えていず、そのために死に興味を引き立てられているようだった。
在宅での死を描いているので「病院で死ぬということ」の対になる作品かと思うが、基本的には教師の父親と息子を描いた作品。いや、あるべき教師の姿を描いた作品と言うべきか。在宅での死の詳細は意外に描かれていない。それがテーマならば、もっと描写を多くしていたはずだ。「あおげば尊し」というタイトルからして、これが教師の映画であることは明白だろう。悪くない映画と思ったけれど、葬儀の場面をもっと効果的にする演出はあっただろうという思いもある。父親と教え子たちの間に何らかの伏線があっても良かったと思うのだ。唐突に始まる「仰げば尊し」の歌だけで父親の教師としての在り方を象徴するのには少し無理があるのではないか。在宅での死か教師の在り方か、どちらかにもっと焦点を絞った方が良かったのではないかと思う。マイク・リーの錐でもみ込むような強さがこの映画には欠けている。
2006年06月08日 [Thu]
■ SonicStage CP
バージョン4.0からこの名前になった。Vaioアップデートからダウンロード。91MBもあった。おまけにこの回線は遅くてISDN並みの速度しか出ない。「3gp、mp4 および、m4a形式の音声ファイルの取り込みに対応」というのが新しいらしい。3GPへの変換もできれば良かったんですけどね。
2006年06月12日 [Mon]
■ 日本1−3オーストラリア
こんな負け方はショックが大きいだろうな。見ている方も唖然呆然とするしかない。攻めのオーストラリア対守りの日本という感じに終始した。守りの緊張感が途切れたところで立て続けに失点してしまった。最後の失点などはまったくディフェンスが機能していなかった。攻めに攻めるヒディンク監督のサッカーは4年前とまったく変わっていない。次は頑張ってくれい。
2006年06月17日 [Sat]
■ 「昭和のまぼろし 本音を申せば」
 週刊文春に連載されている小林信彦のエッセイをまとめた8冊目の本。自宅に帰ったら、届いていたので読む。疲れていたので読み始めてしばらく寝てしまい、起きてまた読み、実家に行って酒を飲んだ後も読み、帰ってまた読んで読み終えた。小説はなかなか読み終わらないのにこういうエッセイはすらすら読める。というか、小林信彦の本は好きなので、読めるのだ。
週刊文春に連載されている小林信彦のエッセイをまとめた8冊目の本。自宅に帰ったら、届いていたので読む。疲れていたので読み始めてしばらく寝てしまい、起きてまた読み、実家に行って酒を飲んだ後も読み、帰ってまた読んで読み終えた。小説はなかなか読み終わらないのにこういうエッセイはすらすら読める。というか、小林信彦の本は好きなので、読めるのだ。
毎回感じることだが、論旨のはっきりしている文章を読むとほっとする。この本の中にも「今のような異常な時代になると、<意見がブレない>ことが何よりも大切だと思う。田中知事には日常の別の戦いがあり、麻木久仁子は家庭・子供を守るという立脚点がある。二人とも、外からの強風によって<ブレない>信用があるのだ」(105ページ)とある。
小泉首相批判は以前から徹底していて、「小泉なにがしという小派閥の手代がヒトラーまがいの暴政で国民を苦しめる」(109ページ)という表現がある。今の日本が完璧に戦前の雰囲気になったのは間違いないようだ。小泉首相もあと少しの任期だが、その後が問題。今より良くなるか悪くなるか。一番人気の人ではたぶん悪くなる方に行きそうな気がする。
映画に関しては「ビヨンドtheシー」「ミリオンダラー・ベイビー」「スター・ウォーズ シスの復讐」「奥様は魔女」「タッチ」などに触れてある。「タッチ」の長澤まさみについて、はっきりスター性があると書いている。スターというのはあくまでも主役を張れる俳優のことで、演技はうまくてもどこまでいっても脇役でしかない俳優がほとんどなのだ。
2006年06月18日 [Sun]
■ [MOVIE] 「グッドナイト&グッドラック」
 アカデミー賞6部門ノミネート。1部門も取れなかったが、ジョージ・クルーニーの「シリアナ」での助演男優賞受賞はこれとの合わせ技と考えていいのかもしれない。最初と最後のエド・マローの演説は感動的で、マローがテレビに対して希望を捨てていないのがよく分かる。「テレビは人間を教育し、啓発し、情熱を与える可能性を秘めている。だが、それはあくまでも使い手の自覚次第だ。そうでなければ、テレビはメカの詰まった“ただの箱”だ」。この映画もまたマローの言葉に沿うようにただの娯楽作品ではない。安っぽいヒロイズムやエモーションとは無縁の堅い演出で、圧力をはねのけてジョゼフ・マッカーシー上院議員を批判する番組を作るマローとそのスタッフの姿を真摯に描き出す。マッカーシーの赤狩りは恐怖政治と同じことで、刃向かえば自分の身に火の粉が降りかかかる。それに立ち向かう勇気の必要さを映画を訴えており、いつの時代にも通用する話である。マローを演じるデヴィッド・ストラザーンの厳しい硬質の演技に感心するが、それ以上にこれはクルーニーのスタンスをはっきりさせている映画だと思う。「シリアナ」とこれでクルーニーはハリウッドの良心を一人で背負って見せた。クルーニーはアメリカの自由を信じているのだろう。
アカデミー賞6部門ノミネート。1部門も取れなかったが、ジョージ・クルーニーの「シリアナ」での助演男優賞受賞はこれとの合わせ技と考えていいのかもしれない。最初と最後のエド・マローの演説は感動的で、マローがテレビに対して希望を捨てていないのがよく分かる。「テレビは人間を教育し、啓発し、情熱を与える可能性を秘めている。だが、それはあくまでも使い手の自覚次第だ。そうでなければ、テレビはメカの詰まった“ただの箱”だ」。この映画もまたマローの言葉に沿うようにただの娯楽作品ではない。安っぽいヒロイズムやエモーションとは無縁の堅い演出で、圧力をはねのけてジョゼフ・マッカーシー上院議員を批判する番組を作るマローとそのスタッフの姿を真摯に描き出す。マッカーシーの赤狩りは恐怖政治と同じことで、刃向かえば自分の身に火の粉が降りかかかる。それに立ち向かう勇気の必要さを映画を訴えており、いつの時代にも通用する話である。マローを演じるデヴィッド・ストラザーンの厳しい硬質の演技に感心するが、それ以上にこれはクルーニーのスタンスをはっきりさせている映画だと思う。「シリアナ」とこれでクルーニーはハリウッドの良心を一人で背負って見せた。クルーニーはアメリカの自由を信じているのだろう。
パンフレットによれば、赤狩りは「時代と偶然が生んだデマゴーグ」という。共産主義への恐怖が広がっていた時代の潮流にマッカーシーは運良く乗った。実際には下品で知性も持ち合わせていなかったようだが、そんな人間でも時代によっては社会の中心になってしまうことがあるのだ。とりあえず反共は当時のアメリカでは正義だったろうし、共産主義への支持は悪とされる雰囲気が一気に広まっていった。CBSの報道番組「シー・イット・ナウ」のキャスターを務めていたマローはそんな中で地方紙の小さな記事に目を留める。空軍予備役士官のマイロ・ラドロヴィッチの家族が共産主義であることを疑われ、除隊処分にされかけているという記事。マローとプロデューサーのフレッド・フレンドリー(ジョージ・クルーニー)はこの事件を番組で取り上げ、真相は分からないのに、なぜ除隊処分になるのかと、マローは番組で呼びかける。これがマッカーシーとの戦いの始まり。マッカーシー側も反撃に出て番組スタッフにはさまざまな圧力がかかってくる。
デマゴーグを排除するのにジャーナリズムは知性と勇気で立ち向かう。そうとらえてもいいのだろうが、もっとこの映画は広い範囲を見つめているように思う。勇気と知性の重要さは何もジャーナリストだけには限らない。僕らはついつい権力者の言うことに流されてしまうけれども、マローやフレンドリーのように一人ひとりが物事の本質を見抜く能力を持たなくてはならないのだろう。デマであっても世間を席捲すれば、実際に被害は起きる。ハリウッドでも犠牲者が出た。僕はこの映画で初めてマッカーシーの映像を見た。マッカーシー役に既存の俳優を使わなかったことは正解で、それに合わせたモノクロームの映像がドキュメントタッチの効果を上げている。
先に挙げたマローの演説はジャーナリズムが世間に迎合することを戒めた言葉でもある。安い製作費で視聴率が取れるクイズ番組をCBS上層部は「シー・イット・ナウ」の代わりに放送することにする。報道機関にいる人間がすべてジャーナリストではない。ジャーナリストは外ばかりでなく、内でも戦わなければならない。これまた世間一般の組織にも当てはまることだろう。
■ 日本0−0クロアチア
どちらも決定力のないチーム同士の凡戦としか言いようがない。柳沢はもう先発させなくていいのではないか。大黒と巻を次は先発で。しかし、さすがに中田も中村も疲れていたなあ。あーあ。
2006年06月21日 [Wed]
■ 午後10時から午前4時までの予告編
「Texas Chainsaw Massacre: The Beginning」の予告編にはそういう断り書きがあった。その時間帯にしか見られない。このインターネットの時代にそういう制限はあまり意味がない気がする。アクセスした人のパソコンの時間を調べて、見られないようにしていれば、大したものだが、アメリカ時間を基準にした制限なのでしょうね。
この映画、もちろん「悪魔のいけにえ」の前日談らしい。そういう映画に大した作品がないのと同様のことになる気がする。監督はジョナサン・リーブスマン。IMDBによると、この人、「13日の金曜日」シリーズの新作の監督も務めるらしい。
2006年06月24日 [Sat]
■ [MOVIE] 「マンダレイ」
 ラース・フォン・トリアー監督のアメリカ3部作の第2弾。前半は「ドッグヴィル」と同じような話だなと思い、退屈だったが、後半面白くなる。これは異常な共同体を描いた映画だと思う。終盤、この共同体の真実が明らかになり、それまでの見方を変えざるを得なくなる。こういう話、世間から隔たった狭い集団の中ではよくある話。集団だけの規則を作り、世間とは独立して独自の世界を築き上げていく。サイコな宗教集団などにありそうだ。この異常な世界に入った主人公のグレース(前作のニコール・キッドマンに代わってブライス・ダラス・ハワード)は表面的な部分を見て民主的な改善をしようとするのだが、表面とは違ったねじれた世界なので、そのしっぺ返しを食うことになる。
ラース・フォン・トリアー監督のアメリカ3部作の第2弾。前半は「ドッグヴィル」と同じような話だなと思い、退屈だったが、後半面白くなる。これは異常な共同体を描いた映画だと思う。終盤、この共同体の真実が明らかになり、それまでの見方を変えざるを得なくなる。こういう話、世間から隔たった狭い集団の中ではよくある話。集団だけの規則を作り、世間とは独立して独自の世界を築き上げていく。サイコな宗教集団などにありそうだ。この異常な世界に入った主人公のグレース(前作のニコール・キッドマンに代わってブライス・ダラス・ハワード)は表面的な部分を見て民主的な改善をしようとするのだが、表面とは違ったねじれた世界なので、そのしっぺ返しを食うことになる。
この前半のグレースの行為はほとんどお節介から始まったとしか思えず、そこがこの映画の弱いところ。ただし、終盤の展開で盛り返した印象がある。この映画、正義を振りかざして他国の内政に干渉するアメリカへの皮肉にはなっているかもしれないが、奴隷制度や黒人差別などのまともな批判になっているかというと、全然なっていない。トリアーも本気でそういう趣旨を込めたわけではないだろう(本気なら何か勘違いしている)。「ドッグヴィル」ほどの完成度はないにせよ、これも興味深い話だ。思えば、「ドッグヴィル」は支配と被支配の関係が固定されたことによって村人が邪悪に変わっていく話だった。「マンダレイ」は支配と被支配の関係から抜け出せず、それを維持しようとしてねじ曲がった人々の話と言える
「ドッグヴィル」同様、簡単なセットで映画は展開する。1933年、ドッグヴィルを焼き払ったグレースとギャングの父親(ウィレム・デフォー)はデンバーで縄張りが荒らされていることを知り、アラバマへ向かう。マンダレイという名前の農園で一人の黒人女がグレースに助けを求めてくる。屋敷の中では黒人男がむち打たれようとしているところだった。奴隷制度は70年前に終わったのに、ママと呼ばれる女主人(ローレン・バコール)が支配するこの農園ではまだそれが続いていた。黒人の苦境を見たグレースは父親と別れてマンダレイに残る。女主人は間もなく死ぬが、死ぬ前にグレースにマットレスの下に隠された本を処分するよう頼む。それは農園の決まりや黒人たちを分類した“ママの法律”だった。グレースは奴隷を解放して農園を民主的に改善しようとする。しかし、黒人たちは働かなくなり、小屋を修理しようと庭の木を切ったために農園は砂嵐に襲われる。木は防風林の役目を果たしていたのだ。
グレースが農園に持ち込むのは自由と民主主義で、それまでママの法律に沿って営まれていた農園は多数決で物事を決めるようになる。その結果、グレースには過酷な任務が待ち受けることになる。これは民主主義の皮肉さを描いているのだろうが、展開として優れているわけではない。僕が感心したのはこの集団の異常さで、このあたりはトリアーの本質が出た部分と思う。トリアー、こういう気持ちの悪いシチュエーションを描かせると、本領を発揮する。万人向けの映画ではないが、オリジナリティのある変わった映画であることは確かだろう。
ブライス・ダラス・ハワードはキッドマンほどの美貌はないけれど、清楚な役柄にはぴったり。R-18指定の要因になったと思われる過酷な場面もこなしており、「ヴィレッジ」よりも成長した跡がうかがえる。
2006年06月30日 [Fri]
■ [MOVIE] 「Death Note 前編」
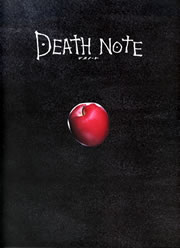 大場つぐみ・小畑健のベストセラーコミックを平成ガメラ3部作の金子修介監督が映画化。警察で対処できない犯罪者を主人公が殺すという始まりは警察内部の私設警察を描いた「黒い警察」や「ダーティハリー2」を思わせるが、この映画の場合、名前を書かれた人間は死ぬというデスノートを使うのでファンタジーっぽい様相がある。ただし、映画の魅力はファンタジーではなく、意外なストーリー展開とキャラクターの面白さの方で、ミステリ的な趣向の方にある。原作漫画を4巻まで読んでみたが、映画の脚色(大石哲也)は原作のエッセンスをコンパクトにまとめてあってうまいと思う。原作には登場しない主人公の恋人にクライマックス、劇的なドラマを用意しており、ここではっきりと主人公がダークサイドに落ちたことを明らかにしている。このあたりの驚きは最初から主人公に悪の雰囲気がある原作にはないものだ。デスノートの元の所有者である死神リュークのCGは良くできていて、原作よりも漫画チックな造型であるにもかかわらず、陳腐にはなっていない。金子修介のエンタテインメントの資質が良い方向に働いたと思う。2時間2分の上映時間のうち、少し冗長と思える部分もあるが、第2のキラと死神が加わって、夜神月(ライト)とLの対決が本格化する後編が楽しみになった。
大場つぐみ・小畑健のベストセラーコミックを平成ガメラ3部作の金子修介監督が映画化。警察で対処できない犯罪者を主人公が殺すという始まりは警察内部の私設警察を描いた「黒い警察」や「ダーティハリー2」を思わせるが、この映画の場合、名前を書かれた人間は死ぬというデスノートを使うのでファンタジーっぽい様相がある。ただし、映画の魅力はファンタジーではなく、意外なストーリー展開とキャラクターの面白さの方で、ミステリ的な趣向の方にある。原作漫画を4巻まで読んでみたが、映画の脚色(大石哲也)は原作のエッセンスをコンパクトにまとめてあってうまいと思う。原作には登場しない主人公の恋人にクライマックス、劇的なドラマを用意しており、ここではっきりと主人公がダークサイドに落ちたことを明らかにしている。このあたりの驚きは最初から主人公に悪の雰囲気がある原作にはないものだ。デスノートの元の所有者である死神リュークのCGは良くできていて、原作よりも漫画チックな造型であるにもかかわらず、陳腐にはなっていない。金子修介のエンタテインメントの資質が良い方向に働いたと思う。2時間2分の上映時間のうち、少し冗長と思える部分もあるが、第2のキラと死神が加わって、夜神月(ライト)とLの対決が本格化する後編が楽しみになった。
ガメラが登場してもおかしくない空撮で映画は始まり、ガメラのようなタイトルで物語が始まる。タイトル前にデスノートの効果を示すのが分かりやすい語り口。そこから映画は少しさかのぼってライトがデスノートを手にした経緯を語る。原作の高校生ライトはデスノートを拾ったことで、殺してもいい人間として犯罪者を選ぶが、映画のライト(藤原竜也)は司法試験一発合格の大学生で、裁ききれない犯罪者への怒りを感じてデスノートを利用する。犯罪のない新しい世界を作ろうと意図する善の男なのだ。ライトは次々に重犯罪者を殺していき、世間からキラと呼ばれるようになる。警察はキラの行為は大量殺人として、これまでさまざまな難事件を解決してきたというL(松山ケンイチ)に協力を仰ぐ。Lはライトが関東地方に住むことを突き止め、捜査情報が漏れていることから内部に関係者がいると見抜く。ここからライトとLの駆け引きが描かれていく。これに絡むのがFBI捜査官の恋人をライトに殺された南空(みそら)ナオミ(瀬戸朝香)。ナオミはライトを怪しいとにらみ、周辺を調べ始める。
ライトは超エリートで悪の主人公なのだが、演じるのが藤原竜也なので脚本の意図通り、単純な悪人には見えない。対するLのキャラクターはいかにも変人で不気味なメイク。善と悪が入れ替わってもおかしくない作りなのが面白い。脚本は原作の設定を尊重しながら、原作にはないさまざまなエピソードを取り入れている。知略を尽くしたライトとLの戦いというのは映画の方がより分かりやすく描かれているし、犯罪者たちの死の描写を取り入れたことでドラマに厚みもあると思う。脚本の大石哲也はこれまでテレビのミステリドラマが中心で、この映画のミステリ的な雰囲気もそれが功を奏したのかもしれない。
ライトの恋人を演じる香椎由宇は、犯罪者はあくまで法律で裁くべきというライトとは対照的な考え方の持ち主として描かれ、非日常的な物語を抑える役目を果たして好演。ライトの父親の鹿賀丈史も堂々とした演技で良かった。
