レクイエム・フォー・ドリーム
 ヒューバート・セルビーJr.(「ブルックリン最終出口」)の原作をダーレン・アロノフスキー(「π」)が監督。エレン・バースティンはこの作品でアカデミー主演女優賞にノミネートされた。「夢への鎮魂曲」というロマンティックな題名とは裏腹の凄まじい描写に終始する。ドラッグに押しつぶされた4人の男女を描いて、話としては類型的なところもあるのに、出来上がった映画は独特のものになっている。その要因がバースティンの凄絶な演技であり、細かいカット割りを多用したアロノフスキー独特のビジュアルなタッチなのである。夏、秋、冬の3章で構成され、その通りのイメージで映画は悲劇を加速していく。それでも見終わった後の印象がそれほど悪くないのは4人が落ちるところまで落ち、これ以上悪くなりようがないからだ。これからは希望にあふれる春に向かうのではないか。ジェニファー・コネリーの圧倒的に隠微なセクシーさも含めて、この映画にはビジュアルな力が充満している。
ヒューバート・セルビーJr.(「ブルックリン最終出口」)の原作をダーレン・アロノフスキー(「π」)が監督。エレン・バースティンはこの作品でアカデミー主演女優賞にノミネートされた。「夢への鎮魂曲」というロマンティックな題名とは裏腹の凄まじい描写に終始する。ドラッグに押しつぶされた4人の男女を描いて、話としては類型的なところもあるのに、出来上がった映画は独特のものになっている。その要因がバースティンの凄絶な演技であり、細かいカット割りを多用したアロノフスキー独特のビジュアルなタッチなのである。夏、秋、冬の3章で構成され、その通りのイメージで映画は悲劇を加速していく。それでも見終わった後の印象がそれほど悪くないのは4人が落ちるところまで落ち、これ以上悪くなりようがないからだ。これからは希望にあふれる春に向かうのではないか。ジェニファー・コネリーの圧倒的に隠微なセクシーさも含めて、この映画にはビジュアルな力が充満している。
サラ・ゴールドファーブ(エレン・バースティン)は古びたアパートに住む孤独な老女。夫は既に死に、一人息子のハリー(ジャレッド・レト)はいつもぶらぶらしている。映画はハリーが家のテレビを質屋に持ち込もうとする場面で始まる。テレビだけが生き甲斐のサラは抵抗するが、結局、質屋に持って行かれてしまう。スプリット・スクリーンを使った緊張感あふれる場面で、もう映画に引き込まれてしまうが、こんなのは序の口。ある日、サラにテレビ局から電話がかかる。いつも見ている番組に出てくれとの案内だった。サラは有頂天になり、ハリーの高校卒業の際に着た赤いドレスをクローゼットから引っ張り出すが、太って着られなくなっている。ショックを受けたサラはダイエットを決意。しかし、食事制限ではうまくいかず、医者から薬を処方される。朝、昼、晩の服用でサラは徐々にその薬の中毒になっていく。一方、ハリーはテレビを売った金でヘロインを買う。既に軽い中毒状態にあり、やはり中毒の恋人マリオン(ジェニファー・コネリー)、友人タイロン(マーロン・ウェイアンズ)とともにヘロインの密売に手を出す。うまくいったのは初めだけ。やがてヘロインが手に入らなくなる。あとはお決まりの転落の方程式。ヘロインを買う元手を手に入れるため、マリオンは売春。ハリーとタイロンはヘロインを仕入れるため、フロリダへ向かう。ハリーの腕は注射の打ちすぎで、真っ黒に変色していた。病院で警察に通報され、ハリーは病院に収容されて腕を切断。タイロンは刑務所に服役する。1人残されたマリオンは禁断症状に絶えられず、屈辱的な売春を続けざるを得なくなる。
ハリーを巡るエピソードはよくある話なのだが、監督がヒップポップ・モンタージュと呼ぶ短いカットを連続する手法が極めて効果的に使われている(このモンタージュで、ふと思い出したのはボブ・フォッシー「オール・ザット・ジャズ」)。ドラッグによる幻覚の描写はデヴィッド・クローネンバーグ「裸のランチ」と一脈通じるところもあるが、よりリアルで怖い。そして何より目を覆いたくなるのがサラの中毒症状。サラがテレビに出たいと願うのは現実の生活が絶望的なまでに孤独だからで、赤いドレスに執着するのはそれが幸せだったころの思い出の服であるからにほかならない。赤いドレスを着てテレビに出ることで現状を変えたいとの悲痛な願いが根底にあり、もはや痩せることだけしか頭になくなったサラは薬をやめることができなくなる。終盤、常軌を逸した状態でテレビ局を訪ね、自分の出演する日を聞くサラの描写はバースティンの老醜をさらけ出した演技で凄まじい迫力がある(「サンセット大通り」のグロリア・スワンソンもここまではなかった)。テレビ局の出演依頼というのも誰かのいたずららしいという設定がさらに悲劇を増幅する。精神病院に入れられたサラは電気ショックトリートメントを受け、体がぼろぼろになってしまう。この描写も「カッコーの巣の上で」のジャック・ニコルソンに匹敵するだろう。
パンフレットのインタビューでアロノフスキーはこう語っている。「中毒というのは、時を超えて文化も超えて普遍的なものだと思う。人間は、孤独や虚ろさを埋めるためならどんなことでもしてしまう。現実から逃れるために。そして夢と呼ばれているものを信じようとするんだ」。先鋭的な表現方法とは異なり、アロノフスキーの視点は地に足のついたものである。それが映画をしっかりしたものにしている。ラスト、ベッドの上で胎児のようにうずくまる登場人物たちは、希望にあふれる春と再生の日の訪れを待ちわびているかのようだ。
【データ】2000年 アメリカ 1時間42分 配給:ザナドゥー
監督:ダーレン・アロノフスキー 製作総指揮:ニック・ウェッシュラー ボー・フリン ステファン・シンコウィッツ 原作:ヒューバート・セルビーJr.「夢へのレクイエム」 脚本:ヒューバート・セルビーJr ダーレン・アロノフスキー 撮影:マシュー・リバティーク 美術:ジェイムズ・チンランド 音楽:クリント・マンセル 衣装:ローラ・ジーン・シャノン
出演:エレン・バースティン ジャレッド・レト ジェニファー・コネリー マーロン・ウェイアンズ クリストファー・マクドナルド ルイーズ・レッサー ショーン・ギュレット
ソードフィッシュ
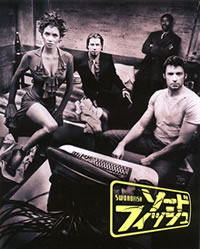
映画は冒頭、「狼たちの午後」(1975年のアル・パチーノ主演映画。アカデミー脚本賞受賞)について延々と話すジョン・トラボルタで幕を開ける。なんだこれはと思っていると、トラボルタ率いる謎の組織が銀行に人質を取って立てこもり、金を奪おうとしているところ。「狼たち…」のパチーノは銀行強盗に成功しなかったが、トラボルタはそれをあざ笑うかのように巧妙な仕掛けを用意して自信満々だ。人質には高性能爆弾が仕掛けられ、銀行から離れると爆発する仕掛け。1人が警察に救助されるが、銀行から離れた途端、大爆発を起こす。パトカーや警官がスローモーションで宙を飛び、爆薬に仕掛けられた弾丸がピュンピュン飛び交うこの場面は秀逸だ。途中、テンポが落ちる場面もあるが、ドミニク・セナ監督(「60セカンズ」)の演出はアクション場面の切れ味がいい。ヒュー・ジャックマンとハル・ベリーの「X-メン」コンビの魅力に加えて、トラボルタがはまり役と言える好演を見せる。同じテロリストが題材の「ダイ・ハード」などに比べると、完成度は落ちるけれど、映画全体にどこかB級の雰囲気が抜けきれていないところにかえって好感が持てる。
世界一のハッカー、スタンリー(ヒュー・ジャックマン)が謎の組織の美女ジンジャー(ハル・ベリー)からスカウトされる。スタンリーは過去にFBIのサーバーをクラックして逮捕され、コンピューターに触ることを禁止された。今はトレーラーに住み、機械の油差しをして暮らしている。最愛の娘は別れた妻が引き取り、思うように会うこともできない。話を聞くだけで10万ドル、成功報酬1000万ドルという条件を聞き、スタンリーは別れた妻から娘を取り返す訴訟費用のため、協力する気になる。組織のボス、ガブリエル(ジョン・トラボルタ)は謎に包まれた人物。天才的頭脳と冷静な判断、冷酷な審判を下す。60秒でサーバーに侵入するテストに合格したスタンリーはガブリエルから政府の闇資金95億ドルをコンピューターで盗むよう命じられる。一方、ガブリエルの動きをつかんだFBIのロバーツ(ドン・チードル)は組織を追跡していた。
冒頭のスローモーションを駆使した爆発シーンから事件の発端となった4日前に飛ぶ構成がなかなかである(「ファイト・クラブ」みたいだが)。「観客全員が騙された」というコピーの割に脚本(スキップ・ウッズ)のミスディレクションは大したことはない。しかし、こういう脚本上の仕掛けは観客に対するサービスなのであり、積極的に評価したい。謎の組織の正体も(結果的に)タイムリーなものになった。この映画、アメリカでは今夏、「パール・ハーバー」を抜いて1位になったそうで、製作者も監督もその時点では、米中枢同時テロのことなど知らなかったのだから、なかなか先見の明(?)がある。もう少し公開時期が遅れていたら、アメリカでは公開が延期されていたのではないか。最後にビンハザード(!)という大物テロリストの名前まで出てくるのだ。「60セカンズ」では芳しい評価を得なかったドミニク・セナ監督はこの脚本を得て、快作に仕上げている。SFXによって何でも表現できるようになった現在、やはり重要なのは話の面白さなのだと思う。
ケチを付けるとすれば、ハッカーの描写で、スタンリーのようにGUIで操作するようなハッカーは超一流とは言えないし、勘に頼ったパスワード破りにもリアリティーがない。コンピューター関係の描写はあくまで舞台設定に過ぎず、マニアには物足りないだろう。スキップ・ウッズはカーチェイスのシーンで「続・激突! カージャック」に言及するなど映画にはマニアックな好みが感じられるけれど、コンピューターにはあまり詳しくないのかもしれない。
【データ】2001年 アメリカ 1時間39分 配給:ワーナーブラザース
監督:ドミニク・セナ 脚本:スキップ・ウッズ 製作:ジョエル・シルバー ジョナサン・D・クレイン 製作総指揮:ジム・バン・ウィグ ブルース・バーマン 撮影:ポール・キャメロン 美術:ジェフ・マン 音楽:クリストファー・ヤング ポール・オーケンフォールド 衣装:ハ・ニューエン 特殊効果:ボイド・シャーミス
出演:ジョン・トラボルタ ヒュー・ジャックマン ハル・ベリー ドン・チードル サム・シェパード ヴィニー・ジョーンズ ドレアド・マッテオ ルドルフ・マーティン ザック・グレニアー キャムリン・グライムス アンジェロ・ペーガン
エボリューション

アイバン・ライトマン監督が「ゴーストバスターズ」(1984年)のノリで作ったエイリアン撃退コメディ。「ゴーストバスターズ」よりも弱いのは出演者にアクの強さがないからか。主演のデヴィッド・ドゥカブニーは基本的にコメディができていないし、転んでばかりいるジュリアン・ムーアはまだしも、短大の地質学講師オーランド・ジョーンズと消防士志望のショーン・ウィリアム・スコットにもう少し存在感がほしいところ。B級コメディアンのドラマを見ているようで、ビル・マーレー、ダン・エイクロイド、ハロルド・ライミス、リック・モラニスと強烈なキャラクターがそろっていた「ゴーストバスターズ」に比べると、見劣りがする(といっても、「ゴーストバスターズ」がそんなに面白かったわけでもない)。ライトマンは近年、「デーヴ」などウェルメイドなコメディを作り、ある程度の評価を得ていたが、再びハチャメチャなSFコメディに戻ってきた今回はどうも演出的に緩い。お気楽な映画だから、お気楽に演出したのかもしれない。
アリゾナ州の地方都市グレン・キャニオンに隕石が落下する。近くの短大で生物学を教えるアイラ・ケイン(デヴィッド・ドゥカブニー)と地質学を教えるハリー・ブロック(オーランド・ジョーンズ)は隕石によってできた洞窟へ調査に行き、隕石から出てきた液体を採種。それは10種類のDNAを含み、急速に進化する生物だった。数日後、2人が学生を連れて再び調査に行くと、洞窟にはナメクジのような軟体動物がびっしり。その生物、空気中では窒息死してしまう。国防省は秘かにケインのコンピューターをハックし、生物の存在を知る。ケインは以前、国防省に勤務しており、開発したワクチンを軍に接種、強烈な副作用(ケイン熱)を起こしたため解雇された過去がある。それ以来、国防省はケインを要注意人物として監視していたのだった。洞窟は軍が管理し、アリソン・リード博士(ジュリアン・ムーア)以下のスタッフが調査。ケインの研究も横取りされる。そのころ街には不思議な生物が出現する事件が相次いでいた。どうやら隕石から出てきた生物が増殖し、地下に張り巡らされた洞窟を伝って出現しているらしい。アイラとハリー、アリソンに消防士志望で隕石落下の現場に居合わせたウェイン(ショーン・ウィリアム・スコット)を加えた4人はエイリアン撃退に乗り出す。
さまざまな宇宙生物を見せるSFXはフィル・ティペットが担当。小さな軟体動物から徐々に進化し、クモやワニや犬をモチーフにしたちょっとグロテスクでユーモラスな生物を作り出している。白眉はショッピング・センターを飛び回る(ラドンやプテラノドンを思わせる)翼手竜のような生物で、いや、これをもっと見たかった。ただし、この生物、翼があるのに手もあるという不思議な造型。ということはドラゴンか。クライマックスに登場するアメーバのようなというか単細胞のような巨大生物にはアイデアが足りないと思う。しかも下品。登場人物が○○まみれになるのは、これまたマシュマロマンの泡をかぶった「ゴーストバスターズ」のラストと同じ趣向だけれど、今回は汚い。いくら前半に伏線があるとはいってもちょっと、これを見た後、食事をする気にはなれない。
【データ】2001年 アメリカ 1時間41分 配給:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント
監督:アイバン・ライトマン 製作総指揮:トム・ポラック ジェッフ・アップル デヴィッド・ロジャース ストーリー:ドン・ジャコビー 脚本:ドン・ジャコビー デヴィッド・ダイアモンド デヴィッド・ウェイスマン 撮影:マイケル・チャップマン 美術:J・マイケル・リーヴァ 衣装:アギー・ゲラート・ロジャース 視覚効果スーパーバイザー:フィル・ティペット
出演:デヴィッド・ドゥカブニー ジュリアン・ムーア オルランド・ジョーンズ ショーン・ウィリアム・スコット テッド・レバイン ダン・エイクロイド イーサン・スプリー マイケル・レイ・バウアー パット・キルベイン タイ・バレル キャサリン・タウン
ムーラン・ルージュ

始まって間もなく映画がユーモアとラブロマンスを混ぜ合わせたような、スラップスティック調のドタバタな描写を見せるあたりで、ユアン・マクレガーがそれを一掃するようにエルトン・ジョン「僕の歌は君の歌」を高らかに歌い上げるシーンに感心した。いや、ホントにうまい。ニコール・キッドマンも下手ではない(歌声が可愛いので驚く)が、マクレガーに比べると少し劣る。この映画、「サウンド・オブ・ミュージック」や「チルドレン・オブ・ザ・レボリューション」(「リトル・ダンサー」でも使われていましたね)「アイ・ウィル・オールウェイズ・ラブ・ユー」(「ボディガード」)「ライク・ア・ヴァージン」「ダイアモンドは女性の親友」(「紳士は金髪がお好き」)などなど過去の名曲を使ってミュージカルに仕立てている。曲の使い方は悪くないし、それなりの効果も挙げているのだけれど、ミュージカルとしてはオリジナルな歌がほしいところだった。バズ・ラーマン(「ダンシング・ヒーロー」「ロミオ&ジュリエット」)のミュージカル好きは分かるのだが、もっと腰を据えてオリジナルの歌から本格的に取り組んだ方が良かったのではないか。姿勢が安易というわけではなく、惜しいのである。どこか偽物の匂いが付きまとうのだ。
1900年のパリ。作家志望のクリスチャン(ユアン・マクレガー)がアパートでタイプを打っていると、天井からアルゼンチン人が落ちてくる。上の部屋ではトゥールーズ・ロートレック(ジョン・レグイザモ)たちがショーの練習をしていた。脚本を書くことでショーに協力することになったクリスチャンはナイトクラブのムーラン・ルージュに行く。華やかなショーを見せるムーラン・ルージュも実は経営は火の車。オーナーのジドラー(ジム・ブロードベント)は伯爵(リチャード・ロクスボウ)の出資を仰ごうとトップスターで高級娼婦のサティーン(ニコール・キッドマン)に相手をさせようとする。ところが、サティーンはクリスチャンを伯爵と勘違い。一目で気に入ったサティーンは部屋でベッドに誘おうとするが、ここで誤解が明らかになる。しかし一度燃え上がった恋の炎は消せない。伯爵の前では無関係を装いながら2人は秘密の関係を続けるが…。
偽物の匂いというのは全編セットの人工的な空間における撮影も影響している。猥雑な描写が多いことで「ロッキー・ホラー・ショー」との比較をよく見かけるけれども、確かにその通りで、主演の2人を除いてはフリークスのような、あるいはフェリーニ的なメイクアップばかりである。男ばかりで「ライク・ア・ヴァージン」を歌うシーンなどは笑うことはできても、(男性には)視覚的にあまり面白いものではないだろう。女優を夢見る高級娼婦と貧しい作家の恋という単純な物語をごてごてに飾り立てたレビューで見せているわけで、どうも好き嫌いがはっきり別れそうな映画である。
基本的にミュージカルは好きなので、退屈はしなかった。短いカット割りを駆使したバズ・ラーマンの演出も技術的には見事なものである。しかし、わくわくするようなシーンはあまりなかった。ムーラン・ルージュで繰り広げられる絢爛豪華なレビューよりも主演2人のミュージカル的場面の方がよほど好ましく、もっとこういう場面を増やせば良かったのにと思う。サティーンが結核という設定も悲劇的側面を煽るだけで不要だろう。こういう話ならハッピーエンドの方がふさわしい。全体的にどうも日本人には濃すぎるテイストのような気がする。 バズ・ラーマン、ミュージカルに対する愛がどこかねじれているのではないか。
【データ】2001年 アメリカ 2時間8分 配給:20世紀フォックス
監督:バズ・ラーマン 製作:マーティン・ブラウン バズ・ラーマン フレッド・バロン 脚本:バズ・ラーマン クレイグ・ピアース 撮影:ドナルド・M・マカルパイン 音楽:クレイグ・アームストロング 音楽監督:マリウス・デブリーズ 音楽スーパーバイザー:アントン・モンステッド 振付:ジョン・オコーネル 衣装デザイン:キャサリン・マーティン アンガス・ストラティー
出演:ニコール・キッドマン ユアン・マクレガー ジョン・レグイザモ ジム・ブロードベント リチャード・ロクスボロウ ギャリー・マクドナルド マシュー・ウィテット クリスティン・アヌー ララ・マルケイ カイリー・ミノーグ デオビア・オパレイ